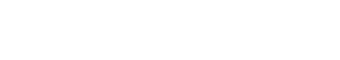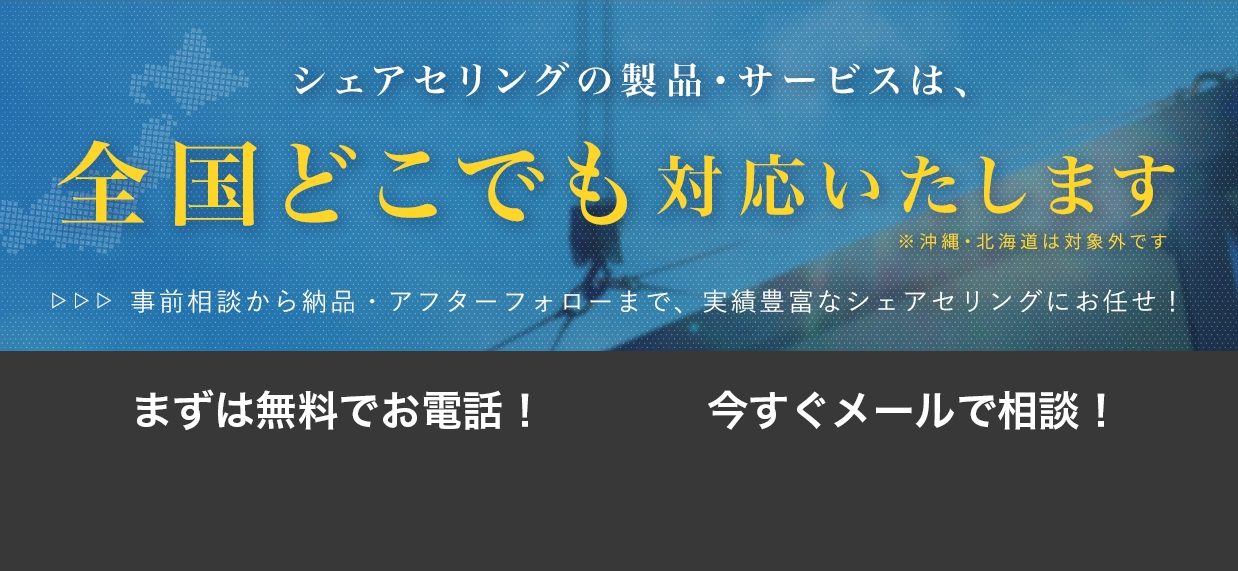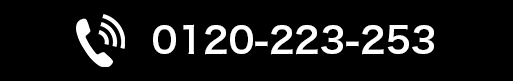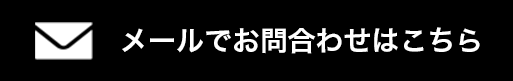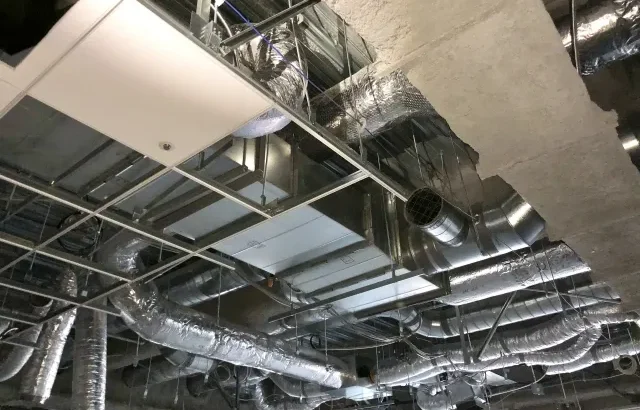特殊引火物は、消防法で定められた第四類危険物に分類されます。
所定数量以上を保管または取り扱う場合は消防法の規制対象となるため、概要を正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、特殊引火物に分類される化学物質を一覧で紹介し、それぞれの特徴を解説します。
また、特殊引火物の概要や取り扱う際の注意点もあわせて解説します。
以下の内容を参考にすれば、特殊引火物の全体像を把握できます。
危険物の基礎知識を確認したい方は、ぜひ参考にしてください。
特殊引火物とは
特殊引火物は、消防法で定められた 危険物の一種で、引火点・発火点が低い、気化しやすいなど特に危険な物質の分類です。
まずはじめに、危険物は次の6種類に分類されます。
| 類別 | 性質 |
| 第一類 | 酸化性固体 |
| 第二類 | 可燃性固体 |
| 第三類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 |
| 第四類 | 引火性液体 |
| 第五類 | 自己反応性物質 |
| 第六類 | 酸化性液体 |
特殊引火物は、第四類危険物の 「引火性液体」に該当します。
消防法における引火性液体の定義は次のとおりです。
引火性液体とは、液体(第三石油類、第四石油類及び動植物油類にあつては、一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る。)であつて、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
さらに、引火性液体は次のように類別されています。
【引火性液体】
- 特殊引火物
- 第一石油類
- アルコール類
- 第二石油類
- 第三石油類
- 第四石油類
- 動植物油類
では、特殊引火物
とはどのようなものなのか、消防法における法的定義は次のとおりです。
特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が一〇〇度以下のもの又は引火点が零下二〇度以下で沸点が四〇度以下のものをいう。
さらに消防法では、分類ごとの引火性液体に関する引火点・発火点などの基準も定められています。
| 引火性液体 | 引火点など |
| 特殊引火物 | ・引火点:-20度以下 ・発火点:100度以下 ・沸点:40度以下 |
| 第一石油類 | ・引火点:21度未満 |
| アルコール類 | - |
| 第二石油類 | ・引火点:21度以上70度未満 |
| 第三石油類 | ・引火点:70度以上200度未満 |
| 第四石油類 | ・引火点:200度以上250度未満 |
| 植物油類 | ・引火点:250度未満 |
見ての通り特殊引火物は、第四類危険物の中でも引火点などが特に低い液体に分類されます。
具体例として、イソプレンやイソペンタンなどが挙げられます。
主な特殊引火物の種類は、後述の「特殊引火物の一覧と詳細」で紹介します。
特殊引火物を取り扱う際の注意点
特殊引火物を安全に扱うために、覚えておくべきポイントは次のとおりです。
【 覚えておくべきポイント】
- 指定数量
- 保管場所
- 取扱者
- 運搬方法
- 混載
ここでは、これらについて詳しく解説します。
指定数量
指定数量は、消防法で次のように定められています。
第九条の四 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)
指定数量以上の危険物を取り扱う、または保管する場合は、消防法の規制対象となります。
危険物の量が増えるほど危険性も高まるため、引火性が高い物質ほど指定数量は小さく設定されています。
引火性液体の指定数量は以下のとおりです。
| 引火性液体 | 指定数量 |
| 特殊引火物 | ・50L |
| 第一石油類 | ・非水溶性:200L ・水溶性:400L |
| アルコール類 | ・400L |
| 第二石油類 | ・非水溶性:1,000L ・水溶性:2,000L |
| 第三石油類 | ・非水溶性:2,000L ・水溶性:4,000L |
| 第四石油類 | ・6,000L |
| 植物油類 | ・10,000L |
例えば、特殊引火物を50L以上保管または取り扱う場合は、消防法の規制を受けます。
また、指定数量の「5分の1以上、指定数量未満」の危険物は、少量危険物として扱われるため、市区町村の火災予防条例で規制されます。
この場合、原則として所轄の消防署へ届出を行う必要があります。
保管場所
危険物を指定数量以上(特殊引火物であれば50L以上)保管する場合は、原則として市町村長などの許可を受けた危険物保管庫(貯蔵所)で保管する必要があります。
消防法で以下のように定められています。
第十条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
参考に、屋内貯蔵所の基準を抜粋して紹介します。
【屋内貯蔵所の基準】
- 見やすい箇所に屋内貯蔵所であることを表示し、掲示板に防火に関する事項を示す
- 独立した専用の建築物を用いる
- 軒高6m未満、床面積は1,000㎡未満の平家建てを用いる
- 壁、柱、床を耐火構造とし、梁に不燃材料を用いる
- 屋根を不燃材料で造り、金属板など軽量な材料で葺く
- 窓、出入り口に防火設備を設ける
- 窓、出入り口にガラスを用いる場合は網入りガラスとする
- 貯蔵所の床は危険物が浸透しない構造とする
- 採光、照明、換気設備を設け、引火点が70度未満の危険物を扱う場合は滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設ける
さらに、保管量に応じて、危険物保管庫の周囲に確保すべき空地の幅も異なります。
出典:e-GOV法令検索「危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)」
取扱者
危険物を指定数量以上扱う場合は、危険物取扱者による管理が求められます。
消防法第十三条3項で以下のように定められています。
製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。
特殊引火物を含む、引火性液体を取り扱う際には、「乙種第4類危険物取扱者」の資格を有する者が必要です。
危険物取扱者免状は、甲種・乙種・丙種に分類されます。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 種類 | 取り扱える危険物 |
| 甲種危険物取扱者 | すべての危険物 |
| 乙種危険物取扱者 | 免状に記載されている危険物 |
| 丙種危険物取扱者 | ガソリン・灯油・軽油・第三石油類(重油・潤滑油・引火点130度以上のもの)・第四石油類・動植物油類 |
つまり、乙種第4類危険物取扱者は、第4類危険物の取り扱いを許可された資格者です。
運搬方法
特殊引火物の運搬は、消防法第16条で定められている運搬の基準を守って行う必要があります。
危険物の輸送方法は、「運搬」と「移送」に区分されます。
それぞれの概要は以下のとおりです。
【運搬と移送】
- 運搬:乗用車や軽トラックなどで容器に入れた危険物を運ぶこと
- 移送:タンクローリー(移動タンク貯蔵所)などで危険物を運ぶこと
乗用車などによる運搬は危険性が高いため、指定数量未満でも消防法の規制対象となります。
運搬に用いる容器の材質・構造・最大容量は「危険物の規制に関する規則」で定められています。
特殊引火物の運搬に利用できる容器は、ガラス容器、プラスチック容器、金属容器です。
収容重量によって、使用できる材質は異なります。
また、運搬容器の外側には、収納している危険物名・数量・注意事項(火気厳禁)などを明記する必要があります。
指定数量以上の危険物を運搬する場合は、黒色の板に黄色の反射塗料で「危」と表示した標識(0.3m四方)を、車両の前後に掲示する必要があります。
混載
第四類危険物は、次の危険物との混載が禁止されています。
【混載が禁止されている危険物】
- 第一類危険物
- 第六類危険物
つまり、法律上は第二類から第五類までの危険物と混載が認められています。
ただし、実際には運送会社が定める規定により、他の危険物と混載できない場合も多くあります。
具体的な規定は事業者ごとに異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
出典:e-GOV法令検索「危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)」
特殊引火物の一覧と詳細
主な特殊引火物には、次の物質が挙げられます。
【特殊引火物一覧】
- イソペンタン
- ノルマンペンタン
- イソプレン
- 二硫化炭素
- アセトアルデヒド
- ジエチルエーテル
- 酸化プロピレン(プロピレンオキシド)
ここでは、これらの特徴を解説します。
イソペンタン
主に発泡剤や溶剤の原料として使用される特殊引火物です。
無色の液体で、独特の臭気があります。
引火点、沸点などは次のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
| 引火点 | -51℃ |
| 発火点 | 420℃ |
| 沸点 | 28℃ |
| 比重 | 0.6 |
| 融点 | -160℃ |
| 溶解度 | 水には不溶(アルコールエーテルなどの有機溶剤とよく混ざりあう) |
高温や酸化剤との接触には十分な注意が必要です。
酸化剤と反応すると火災や爆発を引き起こす危険があります。
また、燃焼により一酸化炭素などを発生します。
ノルマンペンタン
主に溶剤や自動車燃料などの原料として用いられている特殊引火物です。
アミルハイドライド、n-ペンタンなどとも呼ばれます。
無色の液体で、独特の臭いがあります。
引火点、比重などは次のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
| 引火点 | -49℃ |
| 発火点 | 260℃ |
| 沸点 | 36℃ |
| 比重 | 0.63 |
| 融点 | -129℃ |
| 溶解度 | 水に不溶(アルコールなどの有機溶剤とよく混ざりあう) |
引火点が低いため、高温には注意が必要です。
また、強酸化剤と反応して火災や爆発を起こすおそれがあります。
イソプレン
天然ゴムと特徴が似ているイソプレンゴムの原料などとして用いられている特殊引火物です。
2-メチル-1、3-ブタジエンなどとも呼ばれています。
色は無色で、特徴的な臭いを有します。
引火点、融点などは次のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
| 引火点 | -54℃ |
| 発火点 | 220℃ |
| 沸点 | 34℃ |
| 比重 | 0.68 |
| 融点 | -146℃ |
| 溶解度 | 水に不溶(エーテル、アルコールなどとよく混ざりあう) |
揮発性、引火性とも高いうえ、蒸気と空気の混合気体は爆発性を有します。
取り扱いには十分な注意が必要です。
二硫化炭素
殺虫剤や医薬品などに用いられている特殊引火物です。
別名をメタンジチオンといいます。
無色透明の液体ですが、空気に触れると淡黄色になります。
融点、沸点などは次のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
| 引火点 | -30℃ |
| 発火点 | 90℃ |
| 沸点 | 64℃ |
| 比重 | 1.26 |
| 融点 | -111℃ |
| 溶解度 | 水に極めて溶けにくい(エタノールなどとはよく混ざりあう) |
揮発性が非常に高く、引火点・発火点ともに低いため、取り扱いには十分な注意が求められます。
電球の表面に触れて発火することもあります。
また、蒸気と空気が混合すると爆発性を有するため、火気に近づけないことも大切です。
関連記事:化学薬品を保管倉庫で保管するための注意点と取り扱い方法について
アセトアルデヒド
防カビ剤や防虫剤などの原料として用いられている特殊引火物です。
エタノール(アルコール)の中間代謝物として体内でも生成されます。
色は無色で、果実のような臭いがします。
引火点、溶解度などは次のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
| 引火点 | -38℃ |
| 発火点 | 185℃ |
| 沸点 | 21℃ |
| 比重 | 0.78 |
| 融点 | -123℃ |
| 溶解度 | 水、有機溶剤ともよく混ざりあう |
強還元剤、強酸、アミンなどと反応して、火災や爆発を起こすことがあります。
保管時には可燃性蒸気の発生を防ぐため、容器を不活性ガスで封入し密閉する必要があります。
加熱により容器が爆発するおそれがある点にも注意が必要です。
ジエチルエーテル
有機溶剤や麻酔剤などに用いられている特殊引火物です。
エチルエーテルとも呼ばれています。
無色透明で刺激臭があります。
引火点などは以下のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
| 引火点 | -45℃ |
| 発火点 | 175℃ |
| 沸点 | 35℃ |
| 比重 | 0.71 |
| 融点 | -166.3℃ |
| 溶解度 | 水にやや混ざりやすい(エタノールなどとよく混ざりあう) |
空気に触れると爆発性過酸化物を生じることがあります。
引火のおそれがあるため、下記の取り扱いには十分な注意が必要です。
撹拌や流動などの作業中に静電気が発生するおそれがあります。
そのため、静電気放電を防止する対策が求められます。
酸化プロピレン(プロピレンオキシド)
顔料やポリエステル樹脂などの原料として利用されている特殊引火物です。
プロピレンオキシドやメチルオキシランなどとも呼ばれています。
色は無色で、エーテル臭がします。
引火点などは次のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
| 引火点 | -37℃ |
| 発火点 | 465℃ |
| 沸点 | 34℃ |
| 比重 | 0.83 |
| 融点 | -112.1℃ |
| 溶解度 | 水、有機溶剤ともよく混ざりあう |
撹拌、流動などで、静電気が発生することがあります。
空気よりも比重が大きいため、床面付近に滞留し、離れた場所で引火する可能性もあります。
特殊引火物は危険物保管庫で保管しましょう
特殊引火物は、消防法で定められている第四類危険物のひとつで、アセトアルデヒドや二硫化炭素などが挙げられます。
危険性が高いため、指定数量以上を保管または取り扱う場合は、消防法の規制を受けます。
貯蔵所などの基準を遵守し、安全に管理することが重要です。
保管方法でお困りの方は、ワールドシェアセリングにご相談ください。
用途に合わせて選べる危険物保管庫と少量危険物保管庫を、ご購入とレンタルでご用意しています。
手続きでつまずきやすい部分のサポート代行にも対応しています。