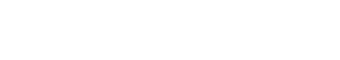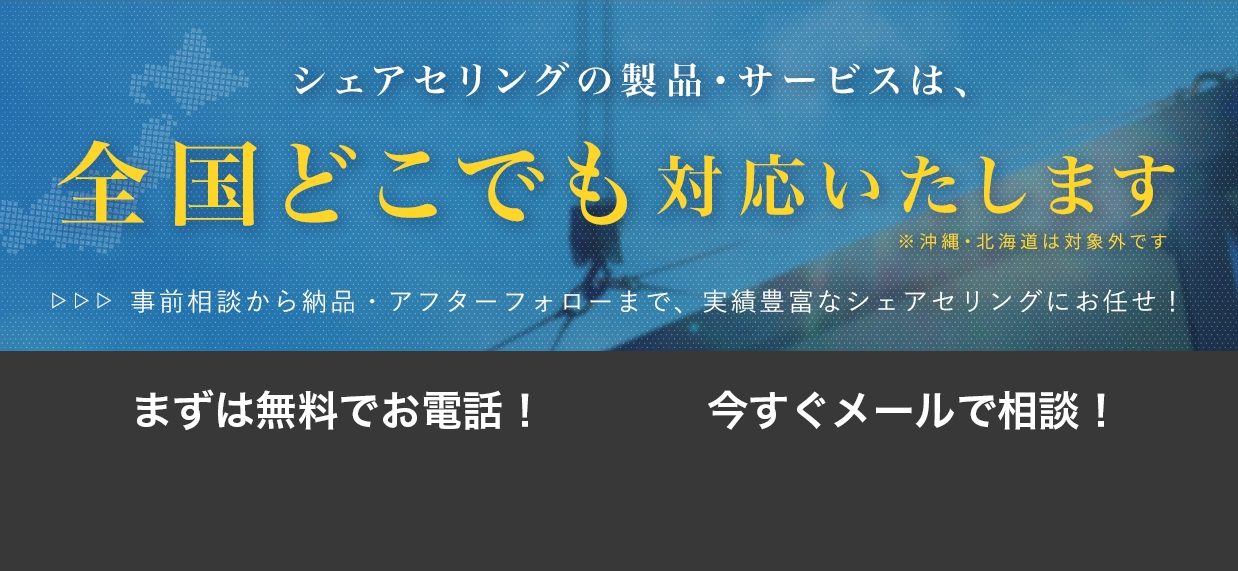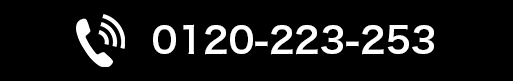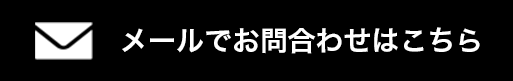倉庫や物置を設置する際は、固定資産税の課税対象になるかどうか正しく理解しておきましょう。
企業や自治体施設などは、建築確認申請や都市計画税の扱いにも関係するため、誤った判断は後々の税務リスクにつながりかねません。
本記事では、倉庫や物置にかかる固定資産税の計算方法や減税措置、課税対象外となるケースまで分かりやすく解説します。
この機会に正しい税金の仕組みを理解しておきましょう。
倉庫・保管庫に固定資産税はかかるのか
倉庫や保管庫は、外見が簡易的であっても一定の条件を満たす場合は「建物」として固定資産税の課税対象になります。
固定資産税は建物や土地などの不動産を所有する人に課される税金で、倉庫や保管庫も対象に含まれます。
企業や自治体の施設では、建物の構造や設置形態が税務上どのように判断されるかが重要なポイントです。
課税対象かどうか判断する際は、次の3つの観点から確認されます。
| 判定項目 | 内容 | 判定のポイント |
| 土地の定着性 | 建物が土地にどの程度固定されているかを示す | 基礎工事などでしっかりと固定され、容易に移動できない場合は課税対象となる |
| 外気分断性 | 建物内部が外気と遮断されているかを示す | 屋根や壁、扉があり、内部空間が外気から保護されている場合は該当 |
| 用途性(登記上の建物に当たるか) | その構造物が目的に応じて利用可能な状態かを示す | 倉庫・保管庫として実際に使用されている場合は課税対象とみなされる |
この3要素のうち、一般的な倉庫や物置は「外気分断性」と「用途性」を満たすケースが多く、最終的には「土地への定着性」が課税判断の基準とされます。
たとえば、基礎工事を伴わないプレハブ型や移動式の簡易倉庫は、定着性がないと判断される場合もあります。
一方で、企業が長期的に利用する恒久的な保管庫や、コンクリート基礎を備えた鉄骨造の倉庫は、固定資産税の課税対象となるのが一般的です。
判断に迷う場合は、自治体の資産税課や税務課へ確認するとよいでしょう。
参考:自治税務局 資産評価室「固定資産評価のしくみについて(家屋評)」
危険物倉庫の場合は課税扱いが異なるため注意
倉庫や物置の固定資産税の判定基準は、一般的な家屋・物置を前提としたものです。
しかし、危険物を保管する倉庫の場合は構造要件が大きく異なるため、一般物置とは区分して考える必要があります。
危険物倉庫には大きく次の2種類があります。
関連記事:危険物保管庫とは?建設に関する消防法・法令と基準をわかりやすく解説
通常建築(増築扱い)の危険物倉庫
工場敷地内に増築するタイプの危険物倉庫は、以下のような構造が求められます。
・コンクリート基礎
・鉄骨造
・耐火構造・防爆構造
これらの条件を満たすため、一般的な物置に適用される「非課税の判断基準」は当てはまりません。
通常建築の危険物倉庫は、固定資産税の課税対象となるのが一般的です。
ユニットハウス式の危険物保管庫
危険物用途のユニットハウス式保管庫は、建築基準法第85条に基づく確認申請が必要で、設置前には基礎工事も必須となります。
そのため、一般的な簡易物置とは異なり、「移動可能な仮設扱い」にはなりません。
また、危険物保管庫として使用する場合は、基礎・アンカー固定・防爆仕様など、建築物として求められる条件を満たす必要があります。
このため、ユニットハウス式であっても、固定資産税の課税対象となるのが前提です。
税務区分や申請内容については、設置前に自治体の資産税課へ確認しておくことをおすすめします。
倉庫・保管庫にかかる固定資産税の計算方法
倉庫や保管庫を新設・購入する際に、「固定資産税がどの程度かかるのか」は気になる点です。
固定資産税は毎年課される税金であり、倉庫の規模や構造によって金額が変動します。
ここでは、倉庫・物置にかかる固定資産税および都市計画税の計算方法を、分かりやすく整理して解説します。
倉庫・物置の固定資産税
倉庫や物置の固定資産税は、原則として「課税標準額 × 税率1.4%」の計算式で求められます。
課税標準額とは、市区町村が建物の構造や用途を基に評価した「固定資産税評価額」のことです。
評価額は通常、購入価格を基準に算出され、自治体の判断によって70〜80%程度に設定されることがあります。
たとえば、300万円の倉庫を設置した場合の固定資産税は次の通りです。
300万円 × 1.4% = 年額4万2,000円
評価額が下がると税負担は減りますが、恒久的な建造物と判断される場合は課税対象から外れないのが一般的です。
特に鉄骨造やコンクリート基礎を有する倉庫は、固定資産税の対象として扱われます。
倉庫・物置の都市計画税
倉庫や保管庫が「家屋」として認められ、かつ設置場所が都市計画法に基づく「市街化区域」内にある場合は、固定資産税に加え「都市計画税」も課税されます。
都市計画税の計算式は、「固定資産税評価額 × 税率0.3%」が基本です。
たとえば、評価額300万円の倉庫であれば、
300万円 × 0.3% = 年額9,000円
となります。
市街化区域とは都市開発を推進するために指定された区域で、人口密度が高く企業や公共施設が集まるエリアを意味します。
したがって、企業用倉庫や危険物保管庫を設置する場合、都市計画税も考慮しなければいけません。
購入費用別の固定資産税・都市計画税の目安
倉庫や物置の購入価格を基にした年間税額の目安をまとめました。
自治体によって評価額が変動するため、あくまで概算として参考にしてください。
| 購入価格 | 固定資産税(年額) | 都市計画税(年額) | 合計税額(市街化区域内の場合) |
| 100万円 | 14,000円 | 3,000円 | 17,000円 |
| 200万円 | 28,000円 | 6,000円 | 34,000円 |
| 300万円 | 42,000円 | 9,000円 | 51,000円 |
| 500万円 | 70,000円 | 15,000円 | 85,000円 |
| 800万円 | 112,000円 | 24,000円 | 136,000円 |
| 1,000万円 | 140,000円 | 30,000円 | 170,000円 |
倉庫や保管庫の導入は、建設費用だけでなく固定資産税や都市計画税といった維持コストも発生します。
そのため、設置を検討する段階から「初期費用+税負担」を含めた総コストを見通しておきましょう。
倉庫・物置の原価償却
倉庫や物置は、購入した時点の価格をもとに固定資産として計上され、原価償却の対象になります。
建物は使用年数に応じて劣化していくため、税務上もそれを反映した評価額の見直しが定期的に行われます。
おおむね3年ごとに再評価され、評価額の低下に伴い固定資産税の負担も徐々に軽くなっていくのが一般的です。
ただし、評価の下限には一定の基準が設けられており、いくら老朽化しても税額がゼロになることはありません。
倉庫や保管庫が存在する限り、最低限の固定資産税は引き続き課されます。
これは、建物が資産としての価値を完全には失わないという考え方に基づいています。
倉庫・物置の固定資産税に対する減税措置
倉庫や物置を設置する際は、固定資産税の課税だけでなく条件を満たすことで受けられる「減税措置」にも注目しましょう。
建物の用途や規模、設置場所によっては税負担を軽減できるケースがあります。
ここでは、代表的な減税制度と申請時の注意点を解説します。
新築住宅に対する減免措置
新築された住宅や事業用倉庫などは、一定期間固定資産税が軽減される制度が設けられています。
一般住宅であれば、新築後3年間(マンションなどの共同住宅は5年間)、建物部分の固定資産税が1/2に減額されます。
認定長期優良住宅の場合はさらに優遇され、5〜7年間の減額措置が受けられるのを覚えておきましょう。
倉庫の場合でも、事業用資産として新築した際に、災害復旧や耐震・省エネ改修を伴う場合は軽減の対象となるケースがあります。
こうした措置は地域の条例や自治体の施策によって内容が異なるため、市町村の資産税課への確認が必要です。
また、地震や火災、落雷などの被害を受けた際も、損害の程度に応じて固定資産税が減免される場合があります。
申請には罹災証明書などの提出が求められ、期限が定められているため早めの対応が必要です。
減税点以下の家屋(小屋)に対する措置
倉庫や物置のうち、課税標準額(固定資産税評価額)が20万円未満のものは地方税法上「課税対象外」とされます。
つまり、建物として認定されても、評価額が基準額に満たない場合は固定資産税が課されません。
この基準は、規模の小さい簡易倉庫や一時的な保管小屋など、資産価値が低い構造物に対し過剰な税負担を避ける目的で設けられています。
ただし、評価額の算定は自治体がするため、販売価格が20万円未満でも評価額が基準を超えるケースもあり得ます。
設置前に構造・基礎・用途などを含め確認しておきましょう。
また、企業が所有する危険物保管庫など、特定の法令に基づいた設計を要する場合は、構造が強固になるため評価額が上がる傾向にあります。
倉庫・物置の固定資産税がかからないケース
倉庫や物置であっても、すべてが固定資産税の課税対象になるわけではありません。
ここでは、実際に非課税と判断されることの多い代表的な条件を解説します。
※以下で紹介するのは、一般家庭用の物置や簡易構造物を想定した基準です。
危険物を保管する倉庫の場合は、ユニット式であっても法令上、基礎工事やアンカー固定、防爆対応などが求められるため、この非課税条件に該当するケースはほとんどありません。
基礎工事を行っていない
基礎工事を行っていない場合は固定資産税がかかりません。
土地に対する定着性が認められなければ、建物として扱われないためです。
たとえば、コンクリートブロックを地面に並べ、その上に物置を置いただけの状態であれば容易に移動できるとみなされ、課税の対象外になる可能性が高いです。
一方で、アンカーボルトやモルタルでしっかり固定されている場合は、恒久的な構造と判断され、家屋として課税されます。
継続して使用しない
一時的な利用を目的とした物置やプレハブも、土地への定着性がないと判断されるため、固定資産税の対象外となります。
たとえば、建設現場の仮設事務所やイベント時の一時保管庫など、期間を限定して使用する場合は恒久的な建築物とはみなされません。
家庭用物置であっても、近い将来に撤去・移動の予定があり、容易に動かせる構造であれば課税対象から外れる可能性があります。
電気の引き込みがされていない
電気設備をもたない倉庫や物置も、固定資産税の課税対象外と判断されます。
「用途性」に関する判断基準であり、照明やコンセントなどを備えている場合は、単なる保管スペースを超えて作業場・事務所としての機能をもつとみなされるからです。
一方、電気の引き込みがなく日常的な作業に使われない収納用物置は用途性が低く、家屋としての機能が限定されるため非課税と判断されることがあります。
倉庫・物置の面積が小さい
床面積が極めて小さい倉庫や物置は、課税対象外と判断される場合があります。
一般的には、4平方メートル(約2.4畳)以下の簡易的な物置は評価額が低く、固定資産税の免税点(課税標準額20万円未満)を下回るため、課税されないケースがほとんどです。
ただし、面積の大小よりも先述した「土地への定着性」「外気分断性」「用途性」の3要件を満たしているかが判断の基準となります。
たとえ小型であっても、基礎工事や電気配線が行われていれば課税対象となります。
倉庫・物置を設置する際に建築確認申請が必要なケース
一定規模を超える物置や防火地域に設置する場合は、建築基準法に基づく「建築確認申請」が必要です。
申請が必要となる代表的なケースを見ていきましょう。
床面積が10㎡を超える建物である
床面積が10平方メートル(約6畳)を超える倉庫・物置を設置する場合は、原則として建築確認申請が必要です。
建築基準法第6条では、一定規模以上の建築物は安全性・耐火性能などを前もって確認することが義務づけられています。
特に鉄骨造や木造で恒久的に利用される倉庫は、構造計算や耐久性の確認が必要となるため、申請を省略することはできません。
一方、コンクリートブロックの上に置くだけの簡易的な設置で、土地に定着していない場合は建築物とはみなされず、建築確認の対象外となります。
防火地域・準防火地域に設置する
設置場所が「防火地域」または「準防火地域」に指定されている場合は、床面積に関係なく建築確認申請が必要です。
これらの地域は火災発生時の延焼防止を目的として指定されており、建築物に厳しい防火構造が求められます。
そのため、たとえ4㎡や5㎡程度の小型物置であっても、防火地域内では燃えにくい素材(耐火構造・準耐火構造)であるか、隣接建物との距離が確保されているかといった点を事前に審査されます。
違反すると是正命令や使用停止措置の対象となるため、消防署および建築指導課への確認は欠かせません。
倉庫・物置を設置する際の注意点
倉庫や物置を「こっそり設置しても大丈夫」と考えるのは危険です。自治体は建築物の把握のために航空写真や現地調査を定期的に行っており、無申請で設置してもほぼ確実に発覚します。
もし未申請のまま設置した倉庫が後から確認された場合、設置した年にさかのぼって固定資産税が課され、未納分に対し延滞税が加算されます。
さらに、建築確認を経ずに設置した場合は、建築基準法違反として是正命令を受けるでしょう。
撤去や構造改修が必要となるケースもあり、結果的にコストが増大することになります。
倉庫・物置の設置前に押さえておくべき固定資産税と法的手続き
倉庫や物置は、課税対象となる条件や建築確認の要否など、複数の法令や税制が関係します。
基礎工事の有無や設置環境によって税負担が大きく変わるため、細かな確認作業が欠かせません。
特に危険物を保管する施設では、消防法や建築基準法への適合が必須です。
安全性とコストの両面から最適な設備を導入するためにも、専門知識をもつ業者への相談をおすすめします。
倉庫・物置の導入や設置に関するご相談は、ワールドシェアセリングまでお問い合わせください。