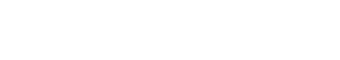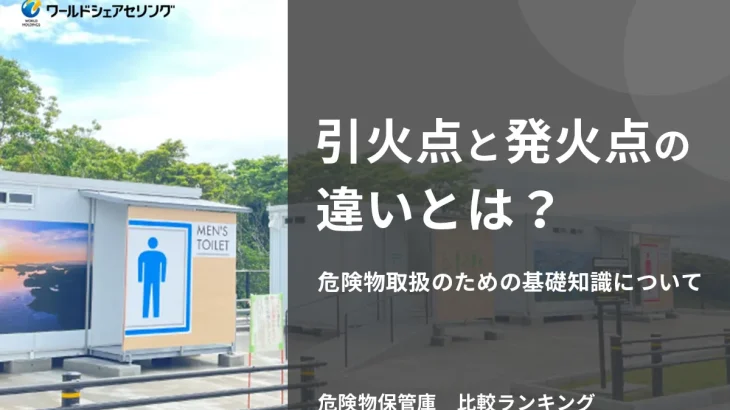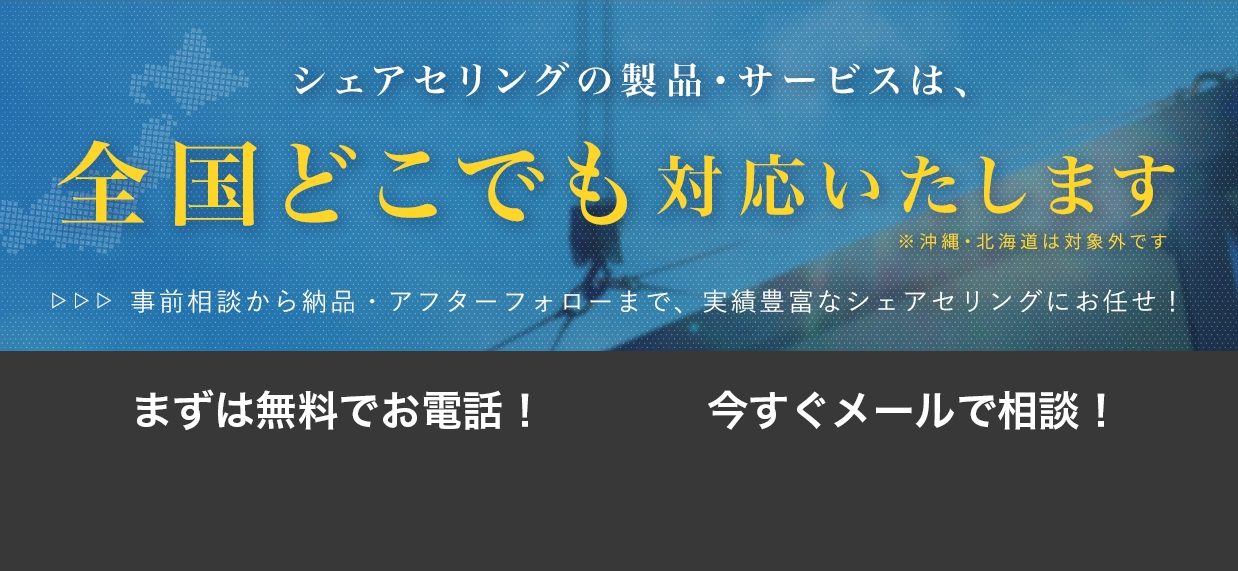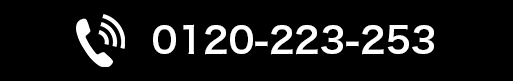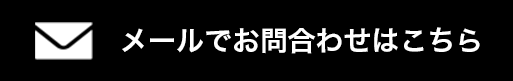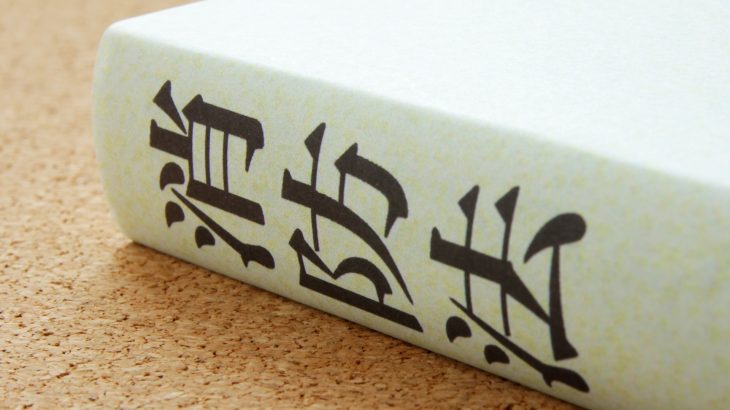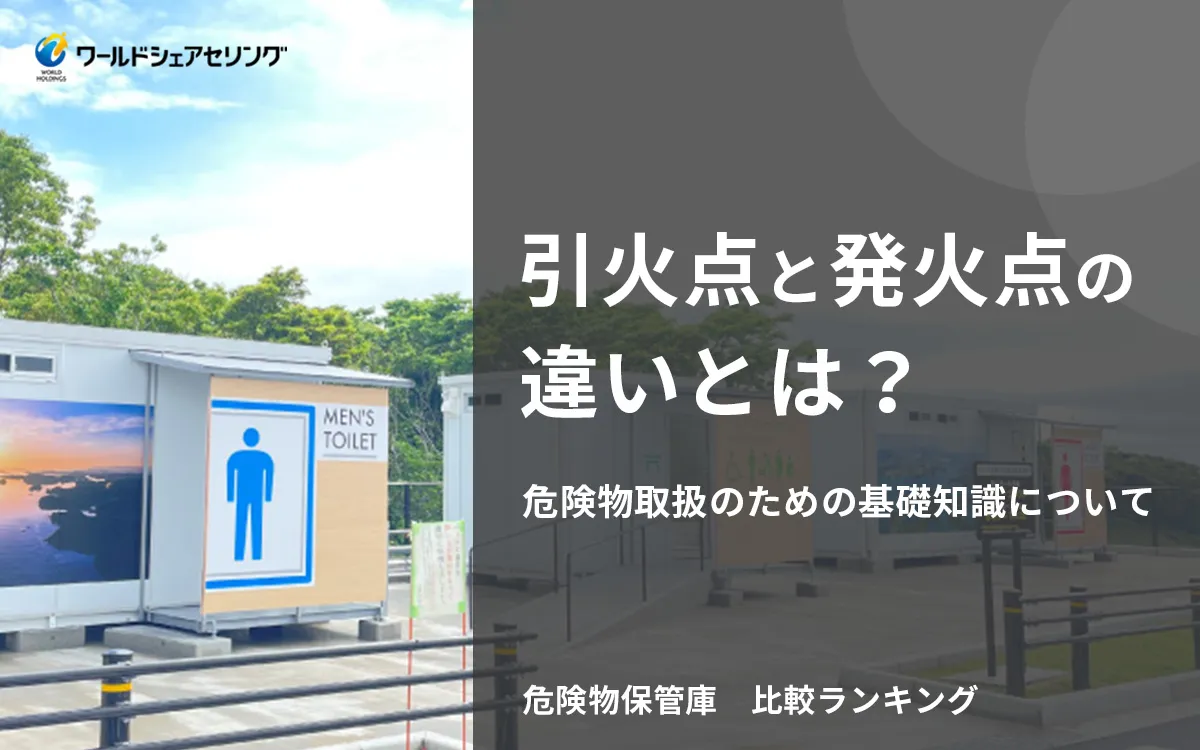
危険物の取り扱い方について調べている方に向けて、引火点と発火点の違いについてご紹介します。
「引火点」と混同されがちなのが「発火点」と「燃焼点」です。これらの違いがわからず、混同してしまう方も多いのではないでしょうか?
そこで今回の記事では、引火点と発火点の違いに加えて、燃焼点と自然発火についても解説します。本記事を参考にすることで、危険物をより安全かつ適切に貯蔵・取り扱えるようになります。
引火点とは
「引火点」とは、可燃性の蒸気が空気中で点火源(火花や炎)によって着火する最低の温度を指します。この温度に達すると、物質は外部の火源によって燃え始めますが、点火源がなければ燃焼しません。
つまり、引火点は「外部の火源がある状態で可燃性蒸気に火がつく最も低い温度」です。
発火点とは
「発火点」とは、外部の火源がなくても、物質が自ら発火する最低温度のことです。
可燃性物質は、高温になると化学反応や酸化反応が促進され、火を近づけなくても自然に発火することがあります。例えば、食用油や工業用油が高温になると自然発火する場合があります。
引火点と発火点の主な違いは次の2点です。
【引火点と発火点の違い】
- 引火点:外部の火源が必要
- 発火点:外部の火源なしで発火
発火点は一般的に引火点よりもはるかに高い温度です。
燃焼点とは
「燃焼点」とは、すでに燃焼が始まった状態で、その火が持続するために必要な最低温度のことです。基準として、引火点に達して燃え始めた後、「5秒以上燃焼が継続する場合」に燃焼点に達していると判断されます。
例えば、引火点で着火した可燃性蒸気が3秒以内に消えてしまう場合、それは燃焼点に達していない状態です。燃焼点は通常、引火点よりも高くなります。
自然発火とは
「自然発火」とは、可燃性物質が発火点に達し、外部の火源なしに燃え始める現象のことです[1]。
自然発火の主な原因には、以下のようなものがあります。
【発熱の原因】
- 酸化:空気中の酸素と不飽和脂肪酸を含む物質が反応して発熱する[2]
- 分解:化合物が成分を分解することによって発熱する
- 吸着:熱を持っている気体や液体の中の分子が固体に吸着し、熱を解放することによって発熱する[3]
- 微生物:微生物の働きによる発酵で熱度上昇が起こり発熱する[4]
通常の状態で保管されていたとしても、さまざまな原因で物質単体で燃え始めます。特に、第4類危険物(動植物油脂など)は自然発火しやすいため、適切な環境で保管することが重要です。
引火点と発火点の違いを把握して火災予防を
この記事を読むことで、引火点と発火点の違いについて理解が深まったと思います。危険物を安全に取り扱うためには、それぞれの物質の引火点・発火点・燃焼点を正しく把握し、適切な保管を行うことが大切です。
ワールドシェアセリングでは、業界内でもトップクラスのラインナップで危険物保管庫をご提供しております。元消防職員も在籍しており、法令に準拠した危険物保管庫をご案内可能です。安全対策のご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
危険物保管庫や少量危険物保管庫・貯蔵庫ならワールドシェアセリングへ
[1]
[2]
[3]
参照:粉体工学用語辞典:吸着熱
[4]