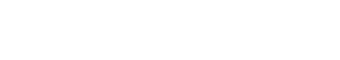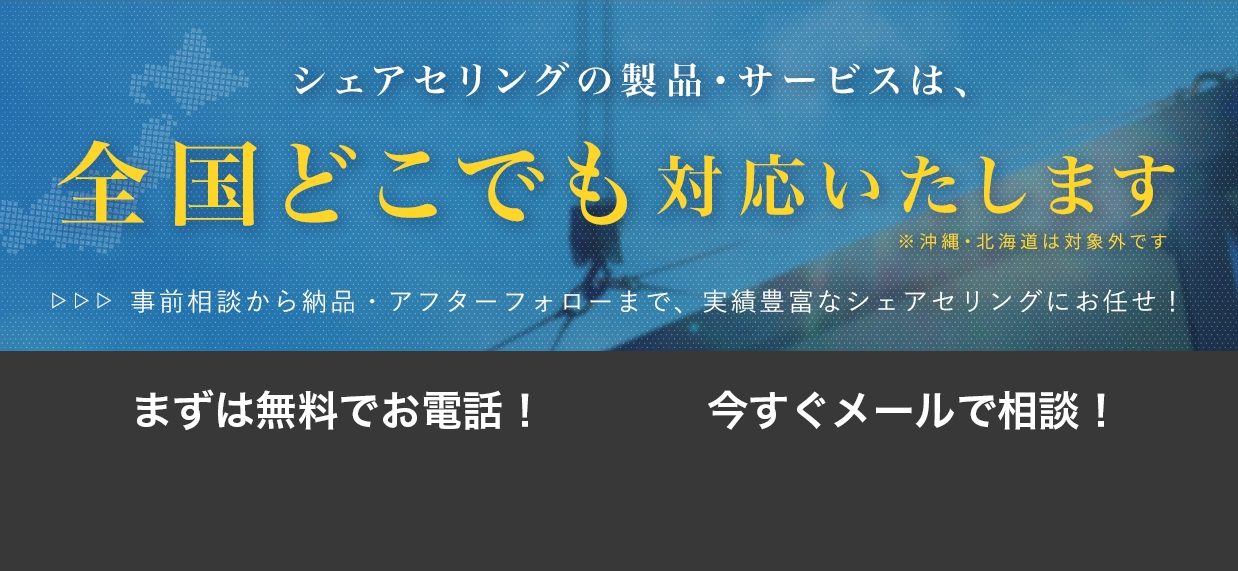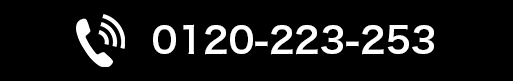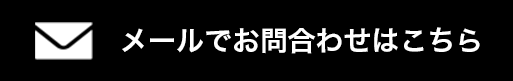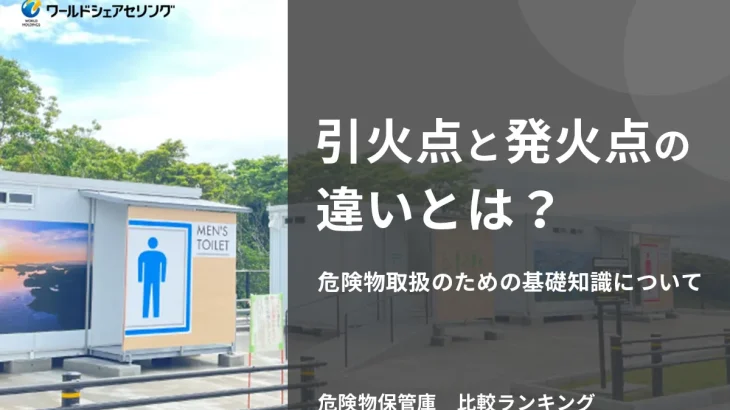少量危険物の取り扱いには、大量の危険物とは異なる規定が定められています。
危険物であっても「少量だから問題ない」と考えて不適切に運搬すると、法令違反となるおそれがあるため注意が必要です。
この記事では、そもそも少量危険物は何かという基礎的な定義から、運搬時に守らなければならないルールまで詳しく紹介します。
運搬時に判断を誤らないために押さえておくべきポイントを解説しますので、ぜひご覧ください。
少量危険物とは?
少量危険物とは、消防法で危険物の種類ごとに定められた「指定数量」に満たない危険物を指します。
危険物とは、以下に該当するものです。
【危険物】
- 火災発生の危険性が大きいもの
- 火災拡大の危険性が大きいもの
- 消火の困難性が高いもの
火災の発生リスクが高く、その被害が拡大しやすいものが危険物に該当することになります。ガソリンや灯油などが代表的です。
危険物には「指定数量」が定められており、その5分の1以上、指定数量未満(個人宅での貯蔵・取り扱いの場合は指定数量の2分の1以上)の危険物 が少量危険物に該当します。
たとえば、ガソリンは指定数量が200Lであるため、少量危険物に該当する量は40L以上200L未満です。
危険物は消防法により規制されており、一定量以上を保管する場合は、条例で定められた基準を満たす施設で取り扱う必要があります。
危険物であっても少量であれば規制が緩いというわけではないので、注意が必要です。
少量危険物も法令に基づいた管理が求められ、運搬時に関する明確なルールも設けられています。
【関連記事】
少量危険物とはどういうこと?定義や保管方法、注意点を解説!
消防法とは?基本内容と罰則についてわかりやすく紹介
少量危険物と少量危険物未満の違い
少量危険物と少量危険物未満では、法令上全く異なる扱いになります。
少量危険物は、指定数量の5分の1以上、指定数量未満(個人宅での貯蔵・取り扱いでは2分の1以上)に該当し、それより少ない数量が少量危険物未満です。
少量危険物を取り扱う場合は、消防署長へ届け出を行い、流出防止措置を講じる必要があります。
取り扱いの詳細については、消防法ではなく各市町村の火災予防条例によって規制されます。
少量危険物未満については、消防署への届け出は不要です。
少量危険物として規制されない少量危険物未満の場合は消防法の規制を受けないことになりますが、仮に保管していた危険物が漏えいして回収が必要となり、費用がかかったような場合は、漏えいさせた人に費用が請求される形です。
そのため、取り扱う量が指定数量未満であっても、安全な管理を徹底する必要があります。
少量危険物と少量危険物未満については、違いを明確に理解しておくことが重要です。両者は別物であることから、現場で混同されることのないように定義と規則の違いをよく確認しておきましょう。
少量危険物を運搬する際に守るべきルール
危険物はたとえ少量であっても、取り扱いを誤れば火災などの重大な事故に直結する恐れがあります。このため、取り扱う量が指定数量未満であっても、安全な管理を徹底しなければなりません。
少量危険物の保管や取り扱いについては各市町村の火災予防条例によって規制されますが、運搬については量に関係なく消防法による規制の対象です。そのため、現場の責任者は、運搬工程ごとにルールを理解し、実行可能な体制を整えることが重要です。
ここでは、少量危険物の運搬に関して運搬容器、積載、方法、混載といった、実務上とくに押さえておくべきポイントを解説します。
運搬容器
危険物を運搬する容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラス、その他総務省令で定められたものとされています。
素材によっては中に入れる危険物と反応してしまう場合があるため、これらについても確認しておくことが重要です。
使用できる容器は、危険物の種類や危険等級によって異なるため、事前に確認しましょう。
また、運搬容器には以下の項目を表記しておきましょう。
【容器に記載すべき項目】
- 危険物名
- I~IIIのうち、該当する危険等級
- 化学名
- 水溶性か否か
- 数量
- 注意事項
危険物用の容器には、破損しにくく漏れを防ぐ構造が求められます。
参考:e-Gov 法令検索:危険物の規制に関する政令第二十八条
積載方法
積載方法の注意点は、運搬する危険物が固体なのか、液体なのかによって異なります。
まず、固形の危険物を運搬する際、内容積の95%以下で収納しなければなりません。
液体の危険物に関しては内容積の98%以下であることに加え、 液体の場合は、55℃でも膨張して漏れないよう、空間容積に余裕を持たせる必要があります。
また、容器を積み重ねる場合は、高さを3m以下にしなければなりません。危険物であるため、運搬中に転落や破損が生じないように積載方法にも注意が必要です。
運搬方法
少量危険物であっても、運搬する際は危険物を運んでいるということを十分に理解し、適切な方法で運ばなければなりません。選択する道路によっては路面状況が悪い場合もあるため、振動や衝撃による事故を防ぐために、容器をしっかりと固定しましょう。
指定数量以上の危険物を運搬する場合は車両の前後に「危」の標識を表示しなければなりませんが、少量危険物であればこのルールは適用されません。
ですが、仮に運搬中に危険物が漏れそうな事態に陥ってしまった場合は応急措置を講ずることが大切です。漏洩や火災はどのような理由で発生するか予測できません。
十分に注意していても他の車などが起こした事故に巻き込まれ、トラックが横転するような事態になれば、安全性が損なわれるおそれもあります。
このような万が一に備え、漏洩や火災による被害を防ぐための対策を取っておくことが求められます。
混載
運搬する危険物によっては、他の荷物と一緒に積載して輸送する場合に危険性が高まる恐れがあります。危険物は第1類から第6類までに分類されており、たとえば第1類は第6類としか混載できません。
詳細な組み合わせは以下をご覧ください。
| 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | |
| 第1類 | - | × | × | × | × | ○ |
| 第2類 | × | - | × | ○ | ○ | × |
| 第3類 | × | × | - | ○ | × | × |
| 第4類 | × | ○ | ○ | - | ○ | × |
| 第5類 | × | ○ | × | ○ | - | × |
| 第6類 | ○ | × | × | × | × | - |
参考:e-Gov 法令検索:危険物の規制に関する規則 別表第4(第46条関係)
なお、こちらの規定は危険物の数量が指定数量の10分の1以下の場合には適用されません。また、危険物と高圧ガスの混載も禁止されているため、十分な注意が必要です。
少量危険物の運搬を依頼する際の運送会社の選び方
自社で少量危険物の運搬を行うのが難しい場合は、専門の運送会社に業務を委託するのも選択肢の一つです。
危険性のあるものを運搬するため、委託先は慎重に選定する必要があります。委託先を誤ると事故やトラブルの原因となり、場合によっては自社の信頼まで失うことになります。
以下では運送会社を選ぶ際に確認しておくべき4つのポイントを紹介します。
危険物運搬の実績があるか
これまでに危険物を運搬した実績がある会社を選択することは何よりも重要といえるでしょう。危険物の取り扱いには高度な安全知識はもちろんのこと、実務経験が求められます。
一般的な運搬物とは温度管理や衝撃緩和などが異なるため、過去の経験に基づき、適切に対応できる会社を選定することが重要です。
実績がある会社では、運搬に関する記録や点検記録などもきちんと整備されています。運送会社を選ぶ際は単純に実績があるかどうかだけではなく、具体的な過去の事例や対応範囲などを確認したうえで検討しましょう。
危険物取扱者が在籍しているか
「危険物取扱者」は国家資格であり、消防法によって定められている危険物を取り扱う際や、その取り扱いに立ち会う際に必要な資格です。
危険物取扱者は危険物の取り扱い方法や消防法に関する知識を有していることになるので、法令違反や事故の発生を防止するためにも欠かせない存在といえます。
危険物取扱者が在籍しているか事前に確認しておきましょう。
安全性への取り組みを行っているか
具体的にどのような安全性の取り組みを行っているかは必ず確認しておきたいポイントです。
たとえば、ドライバーへの安全教育や積載点検記録の管理、安全運転講習の実施などが挙げられます。
最低限の安全対策しか取っていない運送会社を選ぶとリスクが高くなってしまうため、注意しましょう。
厳格な温度管理が行えるか
危険物の中には温度によって危険性が大きく変化するものもあります。そのため、温度管理を厳格に行っている運送会社を選ぶことは欠かせません。
ドライバーが温度変化をモニタリングできる仕組みが備わっているかどうかも確認しておくことが重要です。
少量危険物運搬を依頼する際に必要なもの
少量危険物の運搬を依頼する際は「イエローカード」と「安全データシート(SDS)」が必要です。それぞれの概要と役割、必要性を紹介します。
イエローカード
イエローカードとは、危険物の運搬時に車両内に備え付けなければならない緊急連絡カードのことです。万が一の事故に備え、とるべき応急処置や災害の拡大を防止するための具体的な措置、緊急連絡先などが記載されています。
事故発生時はイエローカードを確認することで速やかな対応につなげることが可能です。
すべての少量危険物に携帯が義務づけられているものではありませんが、少量であっても危険と判断される物品を運搬する際は、事業者の自己責任により携帯の判断を行う必要があります。
安全データシート(SDS)
SDS(Safety Data Sheet)は、化学物質や化学物質を含む製品を安全に扱うために必要な情報が記載された書類です。製品名や提供者である会社の情報、緊急時の連絡先、取り扱い時の注意点などが記載されています。
運搬を依頼する危険物にSDSが添付されていない場合は、供給元に依頼して入手する必要があります。
危険物の取り扱いは少量であっても法令順守と安全意識が不可欠
いかがだったでしょうか。少量危険物の運搬ルールや運送会社の選定ポイントについて解説しました。押さえておきたいポイントについてご理解いただけたかと思います。
危険物は取り扱う量が少ないとしても危険性のあるものなので、注意点をよく確認しておかなければなりません。
危険物を取り扱う場合は、適切に保管することも重要です。ワールドシェアセリングでは、少量危険物保管庫を取り扱っています。
元消防職員が在籍しており、その専門知識を活かして最適な保管庫のご提案やご提供が可能です。ぜひご相談ください。