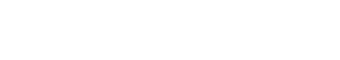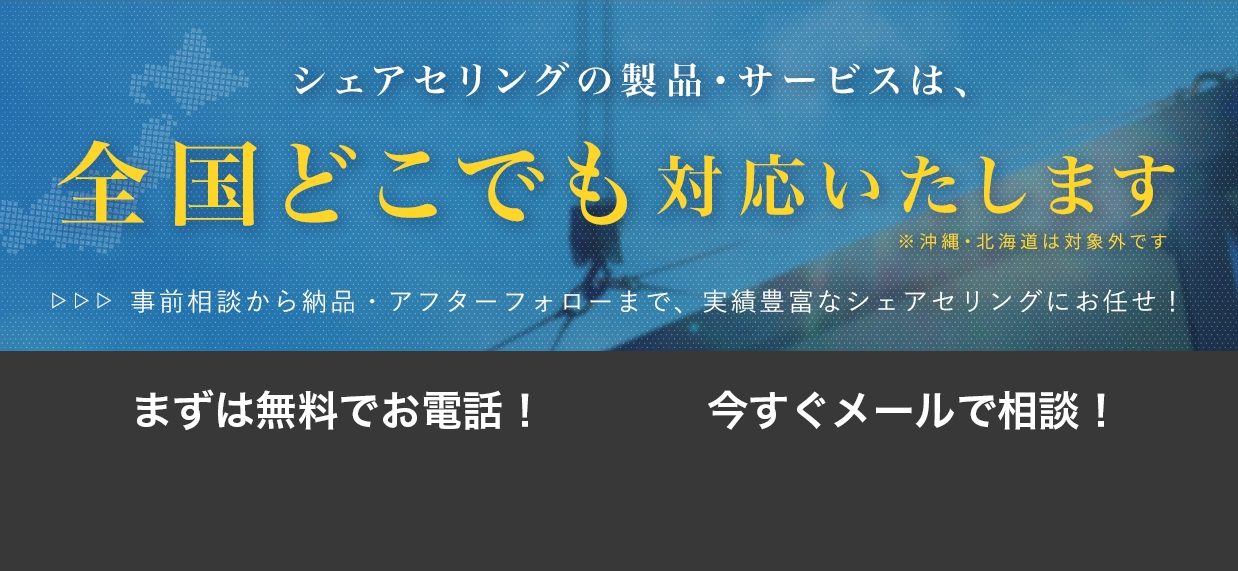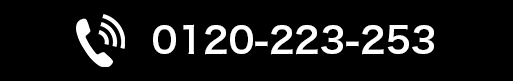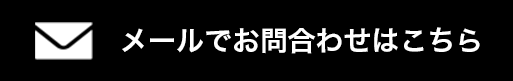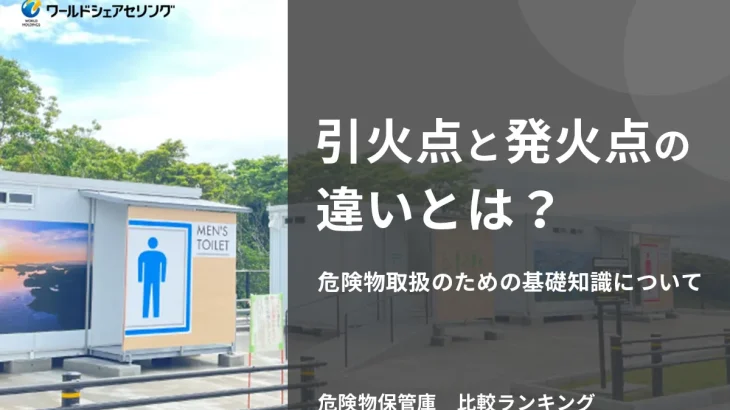危険物の保管と管理を行う危険物倉庫は、万が一の火災や爆発などの事故を防ぐため、法令で厳格なルールが定められています。
倉庫自体の安全性がどれほど高くても、適切な資格を有する人材によって管理・運用されなければ、安全性を維持することはできません。
そこで、本記事では危険物倉庫の管理に重要な資格や選任制度について知りたい方のため、資格・選任制度の種類やそれぞれの役割について解説します。
この記事を読むことで、安全な運用体制を構築するために押さえておきたいポイントがわかるようになるので、ぜひご覧ください。
危険物倉庫とは?
危険物倉庫とは、消防法で「危険物」と定められている物質を保管するための倉庫です。
具体的には、次のようなものが該当します。
【危険物に該当するもの】
- 火災発生の危険性が大きいもの
- 火災拡大の危険性が大きいもの
- 消火の困難性が高いもの
ガソリンや灯油などが危険物の代表例です。
危険物倉庫には、単に危険物を保管するだけでなく、安全に保管・管理できる環境が整っていなければなりません。
取り扱う危険物の種類や量に応じて、倉庫の構造や設備についても細かい基準が定められています。
危険物の種類
危険物は、消防法によって性質ごとに以下の6つに分類されています。
| 類別 | 性質 | 品名の一例 |
| 第1類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物など |
| 第2類 | 可燃性固体 | 硫化リン、赤リン、硫黄など |
| 第3類 | 自然発火性物質および禁水性物質 | カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウムなど |
| 第4類 | 引火性液体 | 特殊引火物、第1石油類、アルコール類など |
| 第5類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物など |
| 第6類 | 酸化性液体 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸など |
危険物の種類ごとに性質が異なるため、事前の確認が重要です。種類によって、必要な取り扱い手順や保管方法も異なります。
また、これから危険物倉庫を準備する場合は、保管する危険物の種類に合わせて倉庫の設備設計や作業マニュアルを用意しなければなりません。
危険度合いを測る指定数量
指定数量とは、危険物の種類ごとに定められた基準となる数量のことで、危険物の危険性を定量的に評価し、保管時の基準量を定めるための指標です。
各種別の品名と性質、指定数量は以下のとおりです。
| 類別 | 品名 | 性質 | 指定数量 |
| 第1類 | 第一種酸化性固体 | 50キログラム | |
| 第二種酸化性固体 | 300キログラム | ||
| 第三種酸化性固体 | 1,000キログラム | ||
| 第2類 | 硫化リン | 100キログラム | |
| 赤リン | 100キログラム | ||
| 硫黄 | 100キログラム | ||
| 第一種可燃性固体 | 100キログラム | ||
| 鉄粉 | 500キログラム | ||
| 第二種可燃性固体 | 500キログラム | ||
| 引火性固体 | 1,000キログラム | ||
| 第3類 | カリウム | 10キログラム | |
| ナトリウム | 10キログラム | ||
| アルキルアルミニウム | 10キログラム | ||
| アルキルリチウム | 10キログラム | ||
| 第一種自然発火性物質および禁水性物質 | 10キログラム | ||
| 黄りん | 20キログラム | ||
| 第二種自然発火性物質および禁水性物質 | 50キログラム | ||
| 第三種自然発火性物質および禁水性物質 | 300キログラム | ||
| 第4類 | 特殊引火物 | 50リットル | |
| 第一石油類 | 非水溶性液体 | 200リットル | |
| 水溶性液体 | 400リットル | ||
| アルコール類 | 400リットル | ||
| 第二石油類 | 非水溶性液体 | 1,000リットル | |
| 水溶性液体 | 2,000リットル | ||
| 第三石油類 | 非水溶性液体 | 2,000リットル | |
| 水溶性液体 | 4,000リットル | ||
| 第四石油類 | 6,000リットル | ||
| 動植物油類 | 10,000リットル | ||
| 第5類 | 第一種自己反応性物質 | 10キログラム | |
| 第二種自己反応性物質 | 100キログラム | ||
| 第6類 | 300キログラム |
たとえば、ガソリンは第4類の第一石油類の非水溶性液体に分類され、指定数量は200リットルです。この数量を超えると、危険物倉庫としての届け出や建築基準法による制限、消防設備の設置義務などが発生します。
200リットルを超えないように管理すれば、規制の対象外となる場合もあります。
危険物を保管する施設の種類
紹介したように、各危険物には指定数量が定められており、これを超える危険物は基準を満たした製造所・貯蔵所・取扱所で取り扱わなければなりません。
それぞれの違いを確認しておきましょう。
| 製造所 | 危険物を製造するための施設です。危険物製造のために建設されており、施設内には常に指定数量以上の危険物が存在しています。 厳格な管理が求められるため、建物の構造だけでなく、設備や配管なども法律で定められた規定に適合している必要があります。 |
| 貯蔵所 | 危険物製造所で製造した危険物を保管するための施設です。指定数量以上の危険物を貯蔵しておくことを目的に建設されます。 屋外タンク、屋内タンク、地下タンクなどのほか、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)などが代表的です。この記事で紹介している危険物倉庫は、危険物貯蔵所の中でも屋内貯蔵所に該当します。 |
| 取扱所 | 指定数量以上の危険物を取り扱い、販売やその他の場所に移すことを目的としている施設です。ガソリンスタンドをイメージするとわかりやすいでしょう。 危険物貯蔵所のように保管を専門とする施設とは異なり、販売や輸送などを目的に危険物を扱うのが特徴です。 |
危険物の取り扱いにおいて重要な資格と選任制度
危険物倉庫で行う業務は、一定の知識・技能を持った有資格者の配置が法律によって義務づけられています。これは、危険物がその性質を正確に理解したうえで取り扱う必要がある物質であり、業務にも高度な知識が求められるためです。
万が一の事故を防ぐためにも非常に重要なポイントといえるでしょう。
とくに危険物取扱者、危険物保安監督者、危険物保安統括管理者の3つの資格・選任制度は、危険物倉庫での業務において重要な役割を果たします。
ここでは、各資格・選任制度の種類と役割に関する重要なポイントを解説します。
危険物取扱者
危険物取扱者とは、一定量以上の危険物を取り扱う際、消防法に基づき配置が義務づけられている国家資格です。
危険物の製造・取り扱い・貯蔵・運搬などに関連する保安の監督者であることを証明する重要な資格でもあります。
危険物取扱者には、甲・乙・丙の3種類の資格があり、このうちどの資格に該当するのかによって取り扱える危険物の種類が異なるので、確認しておきましょう。
各資格では以下の種類の危険物を取り扱えます。
| 種別 | 取り扱える危険物の範囲 |
| 甲種 | 全6類すべての危険物 |
| 乙種 | 指定された第1類~第6類のうち、受験して合格した類の危険物 |
| 丙種 | 第4類(ガソリン・灯油・軽油など)のうち一部 |
それぞれの概要や役割について詳しく紹介します。
甲種
甲種危険物取扱者は、第1類~第6類に該当するすべての危険物を取り扱えます。危険物取扱者の中で最上位に位置づけられる資格です。
甲種を取得することで、さまざまな種類の危険物の保管・移動・取り扱いができるようになります。
このため、危険物倉庫の現場管理者や総括管理者といった役職を担う人材に適しています。
施設によっては複数の種類の危険物を取り扱う場合もありますが、甲種危険物取扱者が1人いれば、第1類から第6類までのすべての危険物を取り扱うことができるため、複数の担当者を配置する必要がありません。
危険物の組み合わせなどを総合的に判断できる甲種危険物取扱者は、現場で欠かせない存在といえるでしょう。
ただし、受験資格に制限があり、以下のいずれかの条件を満たしていなければ受験ができません。
【甲種危険物取扱者の受験資格】
- 大学等において化学に関する学科等を修めて卒業した者
- 大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者
- 乙種危険物取扱者免状を有する者(実務経験2年以上※)
- 修士・博士の学位を有する者
※「第1類または第6類」「第2類または第4類」「第3類」「第5類」のうち、4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者は、実務経験が2年以上なくても認められます。
参考:一般財団法人消防試験研究センター:危険物取扱者試験 受験資格
受験資格には一定の制限がありますが、それに見合う価値がある資格です。
乙種
乙種危険物取扱者は、第1類~第6類の中で、受験して合格した類の危険物のみを取り扱える資格です。乙種は、危険物取扱者試験の中で最も多く受験されている資格でもあります。
令和7年4月~令和7年5月の試験実施状況を見てみると、甲種の受験者が1,043人、後ほど紹介する丙種の受験者が604人であったのに対し、乙種は14,600人が受験しました。
また、乙種の中でも分類によって受験者数は以下のように異なります。
| 分類 | 1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | 6類 |
| 受験者 | 477人 | 520人 | 656人 | 14,212人 | 666人 | 648人 |
受験者数が最も多いのは第4類(引火性液体)で、合格すれば、ガソリン・灯油・アルコールなどが取り扱えるようになります。
合格率も比較的高く、独学でも十分合格を狙える点が魅力です。年齢制限もなく誰でも受験ができるため、実務経験の浅い若い方でも挑戦しやすい資格といえます。
危険物倉庫などの現場では、日常的な管理や作業を担う中心的な存在です。乙種危険物取扱者がいなければ法的に成り立たない現場も多く、非常に重要視されている資格でもあります。
丙種
丙種は、第4類危険物のうち、ガソリンや灯油など特定の引火性液体のみを取り扱える資格です。甲種や乙種と比較すると取り扱える範囲は限られていますが、ガソリン・灯油・軽油・重油・アルコールなど、危険物の中でも身近なものが該当します。
小規模事業所や建設現場などで少量の危険物を取り扱う場合には、丙種で対応できるケースもあります。危険物倉庫においても、簡易的な保管業務などでは丙種で対応できる場合があり、一定の需要があるでしょう。
乙種と同様に年齢を含めて制限はありません。受験難易度も低く、短期間での取得を目指せます。
ただし、複数の危険物を取り扱う倉庫の場合、丙種のみでは対応できません。業務の一部を補助的に担う役割として活躍します。
危険物保安講習の受講について
危険物取扱者の資格は、取得後も定期的に保安講習を受けることが義務づけられています。これは、法令の改正や技術の進歩などに対応するためのものです。
危険物の取扱作業に該当する人が講習を受けなければならないと定められています。
危険物取扱に従事している方であれば、アルバイトや派遣社員も対象です。
前回の講習日から次の4月1日を起点に3年以内に受講する必要があり、原則として3年に1回受講する形となります。各都道府県で実施されているので、該当する方は都道府県の情報を確認しましょう。
対面のほか、オンラインでの参加もできます。
危険物保安監督者
危険物保安監督者は、一定量以上の危険物を扱う現場で、安全管理を統括する責任者として選任される制度です。
甲種または乙種危険物取扱者の資格を持ち、6か月以上製造所などで危険物取扱者として実務経験を積んだ場合に、危険物保安監督者になることができます。
危険物保安監督者は、特定の危険物施設で安全管理のために選任しなければなりません。
そのため、危険物関連の施設で働く場合は危険物保安監督者となることで活躍の幅が広がるでしょう。
危険物保安統括管理者
危険物保安統括管理者は、事業所内の複数の製造所などを統括し、保安管理を行う責任者です。製造所全体の保安業務を統括する役割を担います。政令で定められている製造所などの所有者は、危険物保安統括管理者を任命し、保安業務を担当させる必要があります。
特別な選任要件はありませんが、当該事業所で事業の実施を統括管理できる立場の人であることが条件です。各事務所での保安レベルを標準化し、適切にリスク管理を行っていくために必要な存在といえます。
危険物に関する資格を取得するメリット
危険物に関する資格を取得することで就職やキャリアアップ、さらには収入面にも大きなメリットがあります。主なメリットは以下のとおりです。
就職のチャンスが広がる
危険物取扱者の資格を取得しておくと、幅広い業種で評価されます。危険物取扱者は危険物の取り扱い・保管を行う場合に法令順守のための必須条件です。
特に資格保有者の人材不足が深刻な地方や中小企業では、優先的に採用される場合もあります。
また、事前に資格を取得しておくことで、意欲を示す材料にもなります。
合格を目指しやすい
国家資格の中には合格率が低いものもありますが、危険物取扱者は比較的合格しやすく、独学でも取得を目指しやすい点が魅力です。
令和7年4月~令和7年5月に実施された試験の合格率は、以下のとおりです。
| 甲種 | 乙種1類 | 乙種2類 | 乙種3類 | 乙種4類 | 乙種5類 | 乙種6類 | 乙種計 | 丙種 | 合計 |
| 35.1% | 72.6% | 69.2% | 71% | 38.3% | 68% | 73% | 44.4% | 62.3% | 44.5% |
受験者数が多い関係もあってか、乙種4類は若干合格率が低めではありますが、全体的にみても合格率が低いわけではありません。
働きながら資格取得を目指す方にとっても、取り組みやすい資格といえます。
昇給や奨励金の対象になりやすい
危険物取扱者資格を保有している人は法令クリアのために必要不可欠な人材であるため、給与や待遇面に直結することがあります。
昇給や奨励金の対象となり、毎月数千円から1万円程度の手当が支給されることもあるでしょう。
中には資格奨励金制度を用意しており、取得時に奨励金が支給されるところもあります。
こうした制度も、取得するうえでの大きなメリットです。
危険物倉庫で危険物を取り扱う際の注意点
危険物倉庫で危険物を扱う際は、基本的な安全ルールを守り、常に安全意識を持って業務にあたることが大切です。保管や取り扱いに関するルールを徹底し、万が一の事故を防ぐための対策を講じましょう。
また、火災が発生した場合を想定し、被害を最小限に抑える工夫も必要です。
人的ミスによる事故も多いため、厳格なルールを定め、資格保有者だけでなく現場の全員がそれを遵守することが重要です。全員がリスクを理解し、安全対策に取り組むことが求められます。
資格保有者と条件を満たした危険物倉庫の両方が重要
いかがだったでしょうか。危険物倉庫に重要な資格・選任制度や安全な運用体制について解説しました。安全な運用体制を構築するために、注意すべきポイントもご理解いただけたかと思います。
万が一の事故を防ぐためには、重要な資格保有者を配置することはもちろん、安全性の高い危険物倉庫を選定・導入することも欠かせません。
ワールドシェアセリングでは、所轄消防との事前協議から設置までトータルサポートを行っています。どの倉庫を選べばよいかわからない方や、安全対策について知りたい方は、ぜひご相談ください。