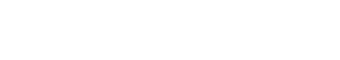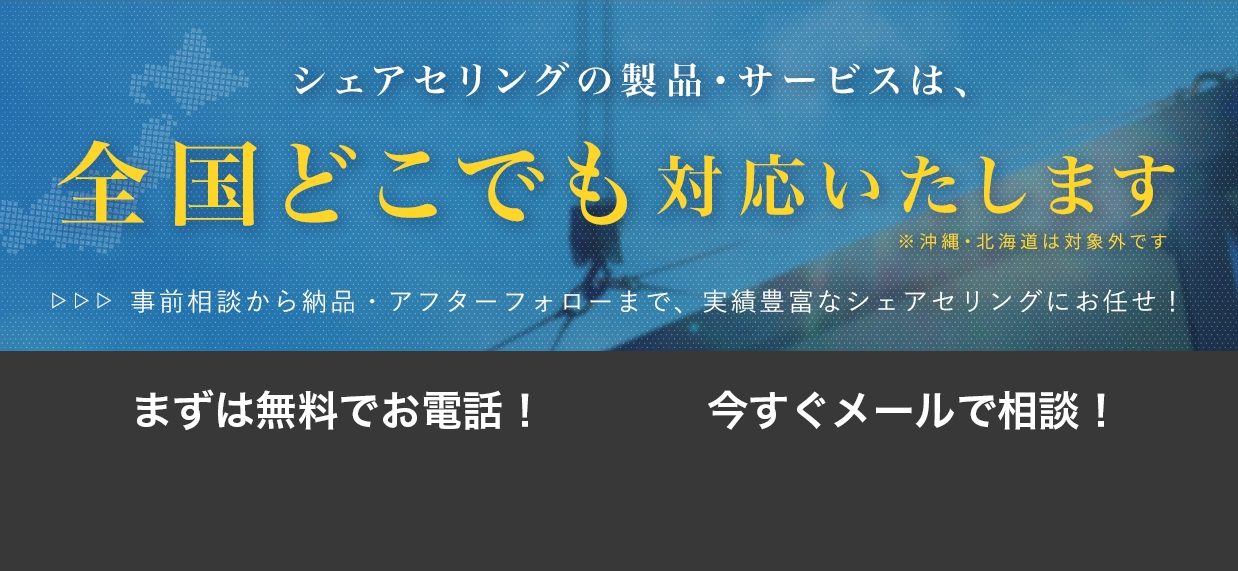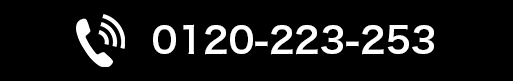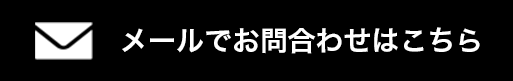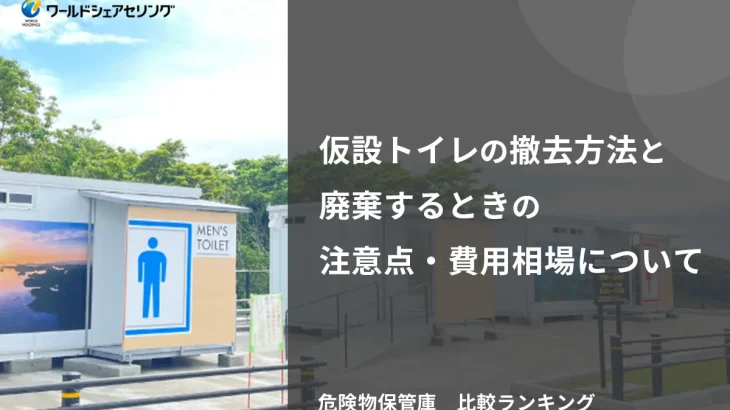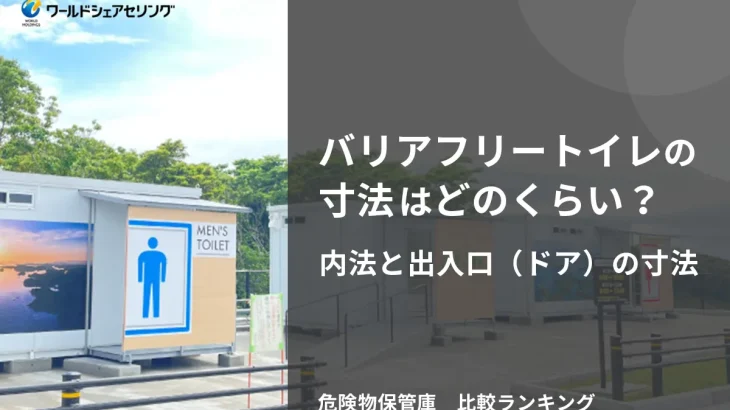避難所に仮設トイレを設置する状況を想定してみたことはありますか。
過去には、トイレの数が足りなかった、女性が使いづらかったといった問題があったため、事前に詳細を把握したうえで計画を立てることが重要です。
ここでは、避難所における仮設トイレの課題を解説し、災害用トイレの種類や選定時に考慮すべきポイントを紹介します。
避難している方が安心して利用できる災害用トイレを見つけたい方は参考にしてください。
避難所の仮設トイレの問題
近年、災害時のトイレ問題は非常に重要視されているポイントのひとつです。
過去の災害によって様々な問題が発生し、健康被害にも直結する重要な課題だからです。
過去の災害時、仮設トイレに関連して浮き彫りになった大きな課題はこちらです。
- 避難者に対してトイレの数が足りていない
- 女性や子どもが使いづらい
これらの課題が引き起こす更なる問題を挙げてみます。
トイレ難民問題
災害発生時、近くの学校や公共施設へ避難することになります。当然、通常利用の範囲を超えて、トイレが不足することになります。
また、仮設トイレの設置には早くても数日程度かかってしまうため、下記のような問題が発生してしまいます。
- トイレ利用者で長蛇の列ができる
- 多数の方が利用するため、清潔な状態を維持できない
これだけであれば、「我慢すればいい」と考える方もいるかもしれません。
しかし、災害時にトイレを我慢しようとすると、重大な健康被害を引き起こす恐れがあります。それがエコノミークラス症候群です。
エコノミークラス症候群の危険
エコノミークラス症候群は簡単に説明すると、「長時間座っていて脚を動かさずにいると、血栓(血のかたまり)ができて、それが肺の血管につまる(肺血栓塞栓症)」という症状です。
トイレが混雑している・汚い、などの問題から水分摂取を控えてトイレに行く回数を減らそうとする方が増え、その結果、脱水症になりエコノミークラス症候群のリスクが高まるのです。
また、水道管の破損など、清潔な水が不足しがちなため手を洗うことが難しくなります。それによって様々な感染症にかかり、更に避難所全体へと拡大してしまうのです。
女性や子どもの利用
先述のようにトイレが不足することで、トイレが詰まったり汚れたり、またそれを綺麗に掃除することも災害時には難しくなります。
仮説トイレが設置されたとしても、従来の簡素な構造の仮説トイレは
- 和式である
- 貯留式になっている
- ニオイや汚れがひどい
- 外からロックが簡単に開けられる、ロックが弱い
- 照明がない、暗い
など、女性や子どもからすると「使えない、使いたくない」理由が多くあります。
関連記事:女性も使いやすい快適トイレ|標準仕様・付属品と仮設トイレとの違い
避難所で使用できる災害用トイレの種類
避難所では、さまざまな災害用トイレを利用できます。
主な種類は次のとおりです。
仮設トイレ
避難所で用いられる仮設トイレは以下の2つにわかれます。
| 仮設トイレの種類 | 概要 |
| ボックス型 | 建設現場やイベントなどで使用することを想定して開発されたトイレ。幅広く流通しているため確保しやすい。耐久性に優れる点も魅力 |
| 組み立て型 | 災害時に使用することを想定して開発されたトイレ。部屋と便器が一体になっている。折りたためるため、保管・搬入しやすい。 |
現在のところ、避難所で用いられる仮設トイレはボックス型が主流です。
災害発生時には交通事情などで、設置に時間がかかる傾向があります。
また、両仮設トイレとも野外での使用を前提としているため、室内外に照明を設置するなどの対策が求められます。
携帯トイレ
何かしらの理由で、排水できなくなった洋式便器に設置して使用するトイレです。
簡単に言えば、尿や便を貯留する袋状の製品です。
吸水シートや凝固剤を使用しているため、水分を安定して扱える点がポイントです。
また、臭い対策が施された製品もあります。
主な特徴は以下の通りです。
【携帯トイレの特徴】
- 保管しやすいうえ単価も安い
- 電気や水を必要としない
- 使用後の携帯トイレを処理しなければならない
ただし、避難所で大人数が使用すると、使用済みトイレの保管場所や臭いの問題が発生する恐れがあります。
マンホールトイレ
下水道管につながるマンホールなどの上に、和式便器、洋式便座、仕切りなどを設置するトイレです。
下水の流れを利用して汚物を流す本管直結型、排水管を貯留槽として活用する貯留型などにわかれます。
主な特徴は以下の通りです。
【マンホールトイレの特徴】
- 一般的な水洗トイレのように使用できる
- 避難所の衛生環境を維持しやすい
- 事前の整備が必要
- 本管直結型などは下流の下水道管が被災すると使用できない
災害時に衛生的に使用できるトイレを迅速に確保できるため、自治体を中心に整備が進められています。
ただし、現在のところすべてのマンホールで使用できるわけではありません。
避難所に指定されている公園や学校に設置されているケースが多いでしょう。
令和3年度末時点の設置台数は42,000基です。
出典:国土交通省「上下水道」
バリアフリートイレ
病気や障害の有無、年齢や性別に関係なく、誰もが安心して利用できるように設計されたトイレです。
具体的には、車いすに乗ったまま入れるトイレ、オストメイト(人工肛門・人工膀胱を造設した方)に対応したトイレなどが例として挙げられます。
たとえば、便座の高さを調整できる組み立て式の仮設トイレなどが登場しています。
ただし、一般のトイレに比べると、その数は多くありません。
快適トイレ
快適トイレは、建設現場を性別に関わらず働きやすい環境に整えるために普及が進められている仮設トイレです。
大規模災害時などは、避難所でも用いられています。
国土交通省が、必須の仕様・付属品を定めている点がポイントです。
| 項目 | 詳細 |
| 必須の仕様 | ・洋式便器 ・水洗機能(簡易水洗などを含む) ・フラッパー機能(臭いの防止機能) ・簡単に開かない施錠機能 ・照明設備 ・荷物置場または衣類かけ |
| 必須の付属品 | ・男女別の表示 ・入口の目隠し ・サニタリーボックス(女性専用トイレ) ・鏡付き洗面台 ・衛生用品 |
出典:(pdf)国土交通省「建設現場に設置する『快適トイレ』の標準仕様決定」
本来は建設現場用の仮設トイレですが、災害時の避難所にも導入されることが今後さらに期待されます。
避難所で使用する災害用トイレの役割分担
国土交通省は、災害用トイレを役割で以下の3つに分類しています。
| 災害用トイレの分類 | 特徴 |
| 携帯トイレ・簡易トイレ | 備蓄しておくと、災害発生直後から使用可能である。最低3日間、推奨1週間分の備蓄が求められている |
| マンホールトイレ | 備蓄および組立が容易。早ければ発災当日から使用できる |
| 仮設トイレ | 備蓄と運搬が難しい。設置までに時間を要する可能性がある。発災3日後からの使用を想定している |
「携帯トイレ・簡易トイレ」を初動で使用し、その後「マンホールトイレ」「仮設トイレ」の順で設置することで、避難所の環境を段階的に整備できます。
それぞれの役割を踏まえて、計画的に準備を進めておくことが重要です。
出典:(pdf)国土交通省「マンホールトイレ整備・運用 のためのガイドライン」
避難所のトイレに関するガイドライン
災害用トイレを確保する際に参考にしたいのが、内閣府が発表している「避難所における トイレの確保・管理ガイドライン」です。
同ガイドラインには、以下の点などがまとめられています。
【女性・子どもに対する配慮】
- 男性用・女性用に分ける
- 生理用品用のゴミ箱を設置する
- 鏡と荷物用の棚、フックを設置する
- 行列を想定して目隠しを配置する
【安全性】
- 室内と経路に照明を設置する
- 施錠できるトイレを用意する
- 防犯ブザーを取りつける
【トイレの個数】
- 災害発生直後は50人あたり1基が目安
- 避難生活が続く場合は20人あたり1基が目安
この他にも、さまざまな内容が記載されています。
災害用トイレの確保に向けて、事前に確認しておくことが重要です。
出典:(pdf)内閣府防災情報「避難所における トイレの確保・管理ガイドライン」
災害用トイレを選ぶ際の事前準備
ここからは、災害用トイレを設置する際に考慮すべきポイントについて解説します。
災害用トイレの種類を把握する
災害用トイレには複数の種類があり、それぞれに特徴があります。
それぞれの特徴は異なるため、詳細を把握したうえで選択することが重要です。
また、同じ種類のトイレであっても、製品ごとに機能や性能が異なる場合があります。
メーカーなどに問い合わせて、強みと弱みを確認しておくことも大切です。
設置場所を決める
災害用トイレ設置場所についても、事前に検討しておくことが求められます。
設置候補地としては、学校の体育館や公民館などが挙げられます。
これらの施設内における設置場所にも注意が必要です。
参考に、意識したいポイントを紹介します。
【設置場所のポイント】
- 暗がりにならない場所を選ぶ
- 高齢者や障害者が使いやすい場所を選ぶ
すべての人が安心して利用できるよう、設置場所の選定に配慮することが重要です。
設置場所のインフラ状況を確認する
インフラによっても、設置できる災害用トイレは異なります。
電気が供給されていれば、照明付きの災害用トイレを円滑に設置できる可能性があります。
設置場所とあわせて、周辺のインフラも確認しておきましょう。
調べておきたい主なポイントは以下の通りです。
【確認するポイント】
- 電気(電源)
- 上下水道
- 隣接する道路
これらの要素を踏まえることで、設置環境に適した災害用トイレを選定しやすくなります。
使用者を想定する
災害用トイレを使用する方も検討しておきたいポイントです。
使用者の属性によって、必要とされる配慮の内容も異なります。
使用者の属性ごとに、求められる配慮のポイントを紹介します。
| 使用する方 | 配慮したいポイント |
| 女性 | ・サニタリーボックスなどを用意する ・簡単に開かない鍵を設置する ・入口に目隠しを取りつける |
| 高齢者・障害者 | ・洋式便器にする ・段差をなくす ・手すりを取りつける ・動線を確保する ・介助者用のスペースを設ける |
| 外国人 | ・掲示物を多言語化する |
使用する方を踏まえたうえで、計画的に準備を進めましょう。
排泄物の処理方法を決めておく
避難所では、排泄物の処理でトラブルになることがあります。
たとえば、便器内に排泄物が溜まるといった事態が想定されます。
処理しきれなかった排泄物は、感染症の拡大や害虫の発生を引き起こす原因となる可能性があります。
したがって、排泄物の保管および処理方法についても、あらかじめ決定しておくことが重要です。
避難所の仮設トイレには快適トイレ・バリアフリートイレがおすすめ
ここでは、仮設トイレを中心に、避難所で使用される災害用トイレについて解説しました。
特徴の異なるさまざまな災害用トイレが用意されているため、使用する方、タイミング、場所などを踏まえて選択することが大切です。
仮設トイレの設置を検討している方は、快適トイレやバリアフリートイレを選んでみてはいかがでしょうか。
年齢や性別、障害の有無を問わず、幅広い方が安心して利用できます。
避難所における複数のトイレ関連課題を包括的に解決できる可能性があります。
製品に関する詳細は、ワールドシェアセリングの快適トイレページをご確認ください。