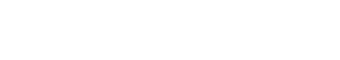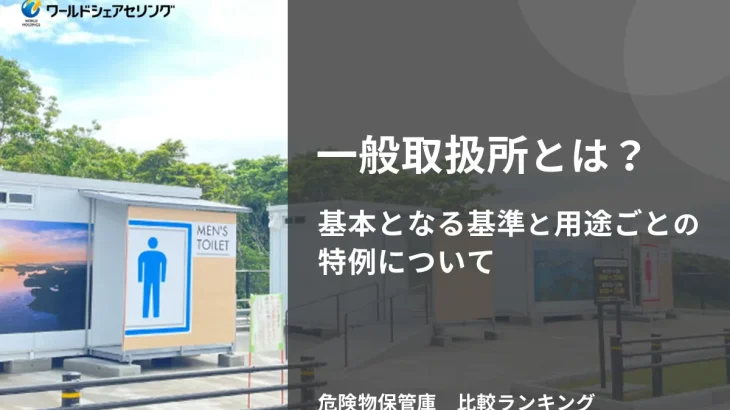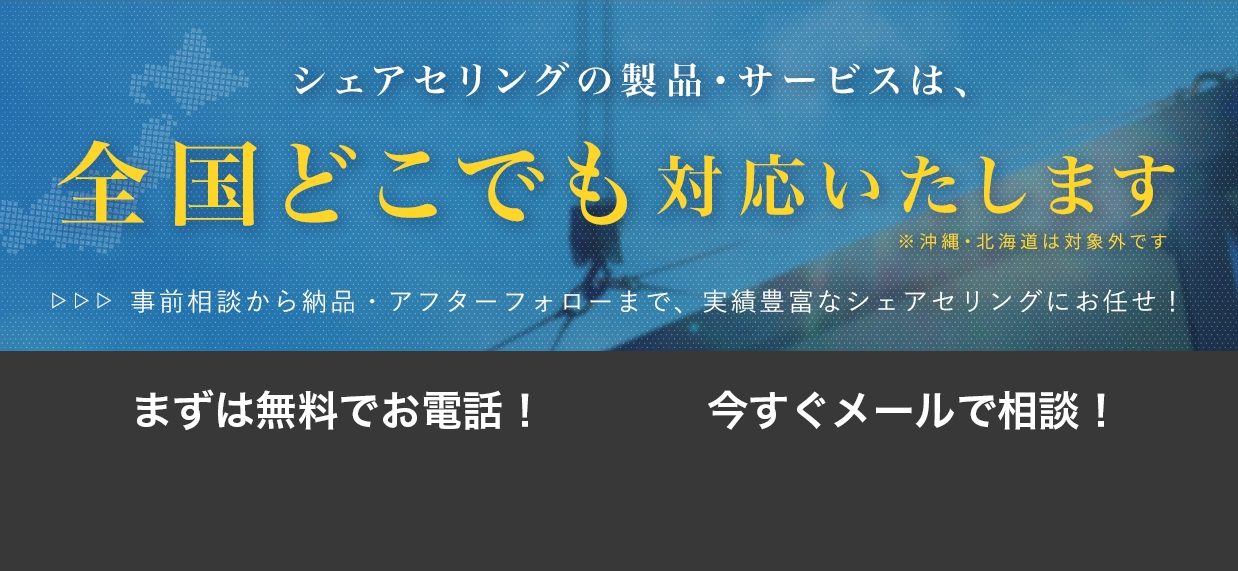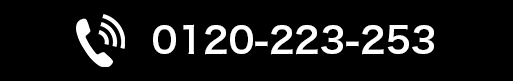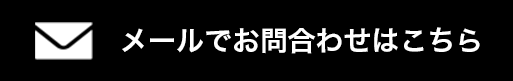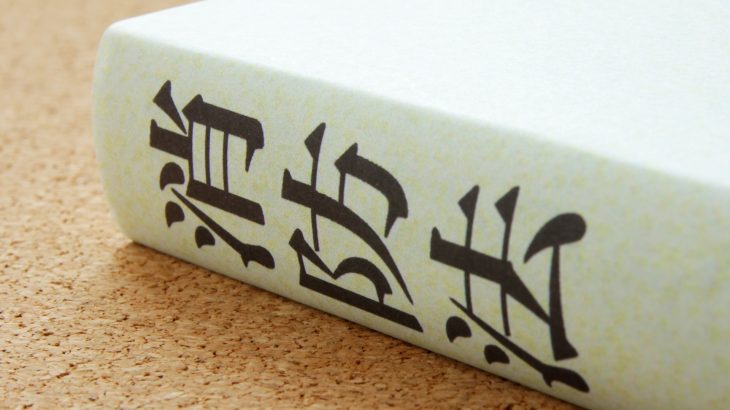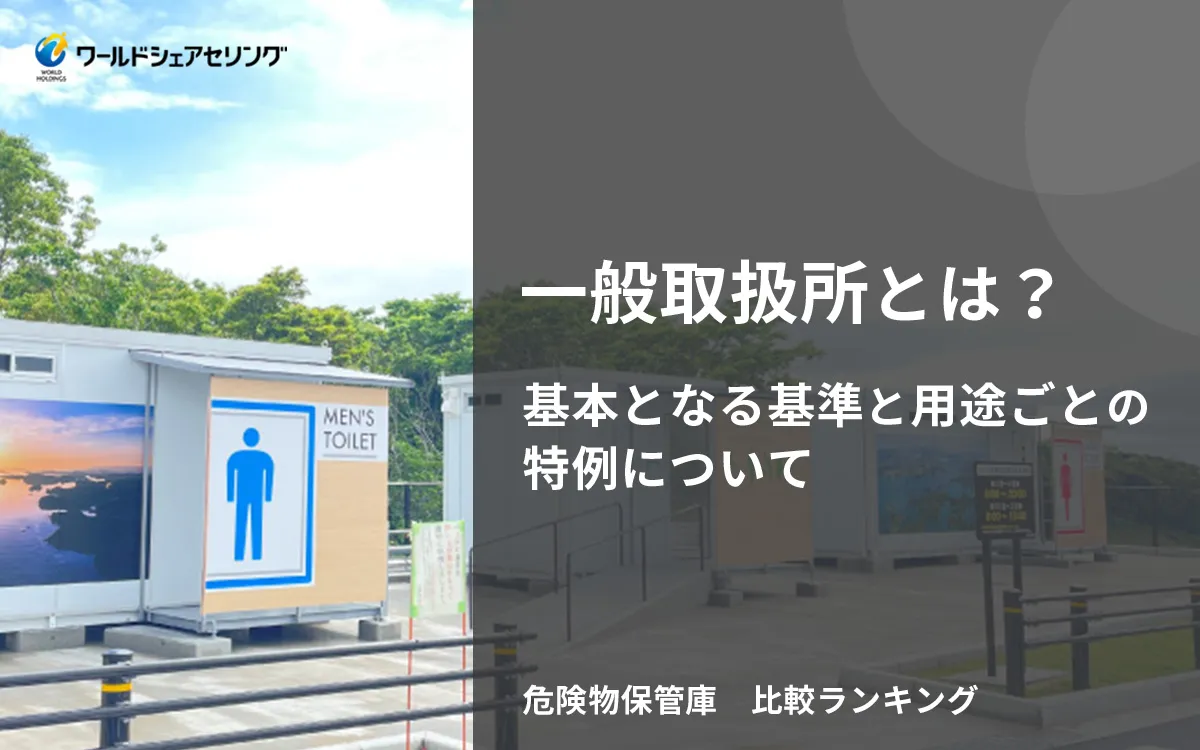
危険物取り扱いについての知識を深めたい方に向けて、一般取扱所とはどのようなものか解説します。
危険物を取り扱う施設にはさまざまな規定が設けられていて、どのように設置すればよいのかわからない方も多いでしょう。さらに給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所以外の施設には、種類ごとに特例が設けられており、制度は複雑です。
そこで今回の記事では、一般取扱所とはどのようなものか、基本的な基準から種類別の特例までご紹介します。危険物を取り扱いたい方、どのように施設を設置すべきか悩んでいる方にとって参考になるはずです。
一般取扱所とは
一般取扱所とは、「給油取扱所」「販売取扱所」「移送取扱所」に該当しない施設のことです[1]。「危険物の規制に関する政令」第3条第4号にて規定されています。
給油取扱所とは、主に燃料タンクに直接給油を行うために危険物を取り扱う施設のことです[2]。販売取扱所は容器に入れられた危険物を販売する施設[2]。そして移送取扱所は配管やポンプなどを使って危険物の移送をする施設のことを指します[2]。上記3つの施設に該当せず、危険物を取り扱う施設を一般取扱所と呼びます。
一般取扱所の基準
一般取扱所の基準は次のとおりです。
【基準】
- 位置:ひとつの建築物内に複数の設置が可能、複数の設備を設置する場合は3m以上の空地を設けること
- 構造:不燃材を使用して外壁は耐火構造とすること、溜めますを設けること、天井を設けないこと
- 設備:蒸気の排出設備、換気設備、防火設備(開口部)、警報設備・避雷設備(指定数量が10倍以上の場合)
基本的な基準は、製造所の基準に準じるものとなっています。ひとつの建物内に複数の施設を設置でき、もし複数の設備を設置する場合は、周辺に3m以上の空地を設けなければなりません[3]。危険物を取り扱う設備ごとに3m以上の空地が必要となるため[3]、2つ並べる場合は6m以上設けてください。
構造には不燃材を使用するのが基本です。また天井がない構造が求められます。外壁は延焼のリスクが高いため耐火構造とし、床には溜めますを設けましょう。
そして一般取扱所では設備に関しても基準が設けられています。上記の排出設備や換気設備、開口部への防火設備の設置が必要です。さらに開口部にガラスを用いる場合は、網入りガラスでなければなりません。指定数量が10倍以上である場合は、警報設備と避雷設備も設置してください。
指定数量とは、消防法の適用の可否を判断するための基準となる危険物の数量です。設備の設置を正しく行うには、危険物ごとの指定数量も把握しておきましょう。
一般取扱所とは基準に沿って設置されなければならないものです。位置・構造・設備のすべてにおいて、基準を正しく把握してください。
一般取扱所の基準の特例
行われる作業によって、基準に特例が設けられています。前項でご紹介した基本的な基準に加えて、次のような特例があることも知っておきましょう。
特例1:吹き付け塗装等の一般取扱所
吹き付け塗装などを行う施設においては、特例として地下や窓、出入り口以外の開口部を設けないことが規定されています。また構造部分の厚みが70mm以上と定められており、特定防火設備を設けることも特例のひとつです。床は、危険物が溜まったり浸透したりしない構造にすることが求められます。
さらに危険物を安全に取り扱うために必要な、採光や照明、換気設備も設けなければなりません。換気設備には防火に役立つダンパーを設置するようにしましょう。
特例2:洗浄作業等の一般取扱所
洗浄などで危険物を必要とする施設の場合、指定数量が特例の条件として定められています。危険物の指定数量が1/5以上であれば、タンクの周辺に囲いをし、熱を加える際には過熱を防止できる装置を設置してください。
そして、指定数量の倍数を計算したうえで、10未満であったときには、構造に不燃材料を用いた平屋にすること、危険物を取り扱う設備を床に固定することが必要です。
施設の基本的な基準では、危険物を取り扱う設備の周りに3m以上の空地が必要でした。しかし洗浄作業などを行う施設の場合、指定数量の倍数が10未満で、壁や柱が耐火構造であるなら3m未満の空地でも認められます。
その他の特例は、前項の吹き付け塗装を行う施設とほとんど変わりません。洗浄作業など行う施設を設置するなら、上記の特例も把握したうえで行いましょう。
特例3:焼入れ作業等の一般取扱所
作業場にて焼入れなどを行う場合にも、指定数量による特例が設けられています。基準は吹付け加工を行う場合と類似していますが、焼入れ作業を行う場合は上階に関する規定が設けられているのが特徴です。また、危険物が発火や爆発を起こす危険な温度に達する前に警報を発することも必要条件のひとつです。
さらに、放電加工機には液温検出装置などの安全装置を設ける必要があります。焼入れ作業を行うなら、第一に火災が起こらないようにより一層注意を払うことが必要です。万が一の発火に備え、警報を発したり消火を行ったりする装置を準備することも重要です。
特例4:ボイラー等で危険物を消費する一般取扱所
ボイラーやバーナーなどの器具を使って危険物を取り扱う施設では、基準の特例が非常に多く設けられています。危険物を取り扱うタンクの容量も定められており、さらにボイラー等には、危険物の供給を自動的に遮断する装置を設ける必要があります。
屋内に危険物用タンクを設けるためには、構造はもちろん、必要な採光・照明・換気を図らなければなりません。地震や停電のときのため、からだき防止装置や過熱防止装置、炎監視装置、停電安全装置を設置することも求められます。
ボイラー等で危険物を消費する施設を設置する場合は、特に基準の特例を詳細に確認することが重要です。
特例5:充填の一般取扱所
続いては充填をするための施設の特例について解説します。
「充填をするための施設」とは、車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等及びアセトアルデヒド等を除く)を注入する一般取扱所を指します。
まず、アルキルアルミニウム等およびアセトアルデヒド等を除く液体の危険物を取り扱うことが可能です。タンクに液体を注入する際にも危険が生じるため、円滑に注入できる広さの空地を確保することが求められます。また万が一危険物が漏れ出した場合に備えて、舗装をすることも重要です。
さらに液体の性質によって、急激な圧力上昇を防止するための装置を設けること、通風のための壁を設けないことも特例となっています。充填を行う施設では、圧力を急激にかけないこと、蒸気が滞留しないこと、危険物が流出しないよう注意が必要です。
特例6:詰め替えの一般取扱所
詰め替え作業を行う施設においては、ホース機器の周囲に固定注油設備を設けられる広さの空地を設けてください。固定注油設備には、危険物をほかの容器に詰め替えるための設備と、車両に固定されたタンクに詰め替えるための設備の両方が含まれます。空地は地盤面よりも高くし、危険物が空地以外に流出しない構造にする必要があります。
また、詰め替えを行う施設の特例の特徴として、危険物を取り扱うタンクを設けてはならないとの規定があります。ただし固定注油設備に接続される30,000Lの専用タンクを地盤下に埋める場合は例外です。地下に専用タンクを埋設する場合は、構造や位置、設備を法令に従って設置しなければなりません。
特例7:油圧装置等を設置する一般取扱所
油圧装置等が設置されている施設であれば、そのほかの施設の特例とそれほど変わりません。構造を不燃材料とした平屋とすること、出入り口以外の開口部を設けないこと、出入り口には防火設備を設けることなどです。またガラスは網入りとすること、危険物を取り扱う設備は床に固定することなどが定められています。
指定数量倍数が30未満である、油圧設備・循環油循環装置を設置する施設では、危険物が浸透しないよう床に傾斜をつけることも特例のひとつです。
特例8:切削装置等を設置する一般取扱所
続いては切削装置を設置している場合の特例についてです。ほかの施設と比較すると、特例の条件は少なくなっています。危険物を取り扱う設備を床に固定すること、危険物が浸透しないように床に傾斜を着けることなど。特例として頻繁に採用されている条件ばかりであるため、比較的容易に遵守できます。
特例9:熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所
熱媒体油循環装置を設置する施設の特例は、危険物の体積が膨張した際に、危険物の漏洩を防ぐ構造にすることのみです。70mm以上の鉄筋コンクリート造で区画を作り、出入り口以外の開口部を設けない耐火構造とすることが求められます。
危険物施設の種類
それでは最後に、危険物施設の種類について見ていきましょう。
種類1:危険物製造所
「危険物製造所」とは、危険物自体の製造を行う施設のことです。(削除しました)危険物が常に大量に保管されていることを前提としています。そのため、法令により建物の構造や設備、配管などが厳格に規定されています。
避雷針・排気口・照明設備・採光設備の設置も必要となります。
種類2:危険物貯蔵所
指定数量を超える危険物を保管・貯蔵する施設を「危険物貯蔵所」といいます。屋内・屋外・移動タンクのいずれも含まれます。タンクローリーも危険物貯蔵所に分類されます。一般的に危険物倉庫と言えば、危険物貯蔵所のことを指します。
種類3:危険物取扱所
「危険物取扱所」は、危険物を取り扱うことをメインとした施設のことです。危険物を製造することはありません。貯蔵を行うだけでなく、移動や使用などの取り扱いも行うことが特徴です。危険物の貯蔵と販売・移動を行うガソリンスタンドは危険物取扱所に該当します。
一般取扱所とは給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所以外の施設
いかがでしたでしょうか?この記事を読んでいただくことで、一般取扱所とはどのような施設であるかご理解いただけたと思います。給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所のいずれにも該当せず、危険物を取り扱うのが一般取扱所です。
ワールドシェアセリングでは、消防管轄から事前協議まで、トータルでのサポートとともに危険物保管庫をご提供しております。種類ごとに特例が定められている施設です。法令遵守の適切な保管庫をお求めなら、ぜひお気軽にご相談ください。
危険物保管庫や少量危険物保管庫・貯蔵庫ならワールドシェアセリングへ
[1]
参照:いわき市役所:(PDF)第4章 一般取扱所(危政令第 19 条)
参照:e-GOV法令検索:危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)
[3]