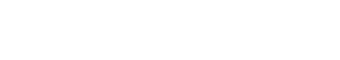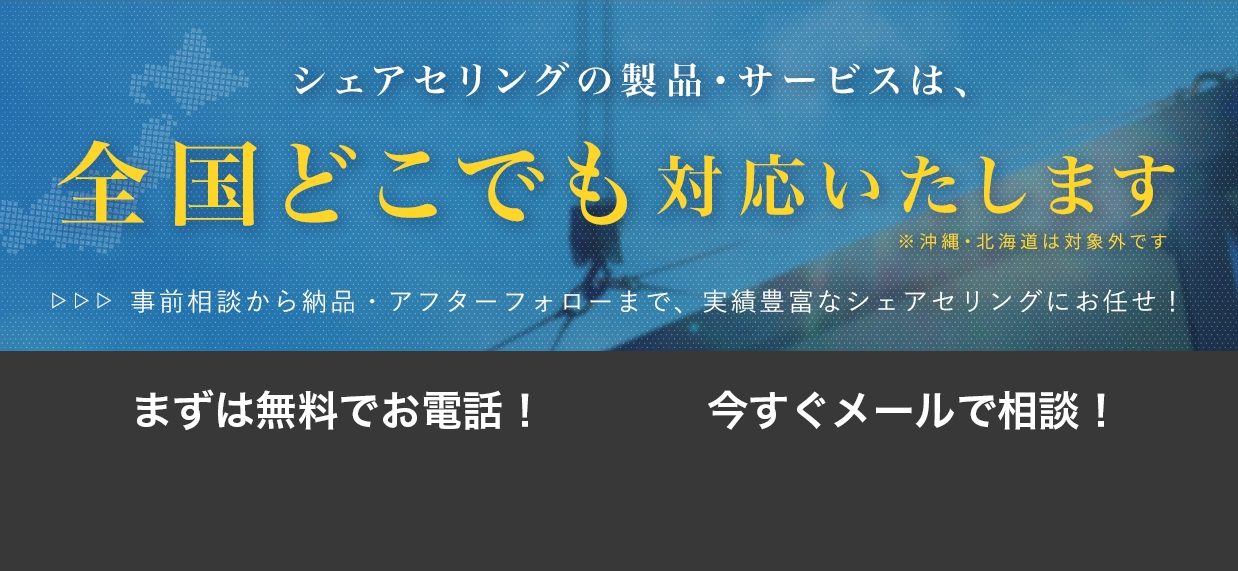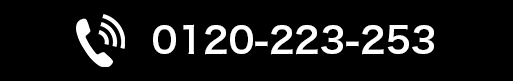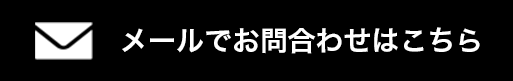私たちの身の回りには、意外な場所に「火災リスク」をはらむ物質が存在しています。そうした物質を安全に管理・使用するために、法律によって分類・規制されているのが「危険物」です。
とくに、倉庫や工場などの施設運営に関わる現場では、消防法に基づく危険物の管理・表示義務が重要です。
本記事では、消防法で定められた危険物の定義や分類、表示義務について解説します。事業者や管理者として知っておくべき知識ですので、参考にしてください。
危険物の定義
消防法における「危険物」とは、火災や爆発、中毒などの事故を引き起こすおそれのある物質で、法令により性状・品名・数量が指定されたものを指します。
消防法第2条第7項では、危険物を「火災の発生、拡大のおそれがある性質を有する物品で、政令で定めるもの」と定義しています。定義に基づき、6つの類別に分類され、それぞれに応じた取り扱い・貯蔵・運搬の基準が設けられているのが特徴です。
具体的な対象には、以下のような物質が含まれます。
- 可燃性が高いもの
- 酸化反応を促すもの
- 自己反応によって燃焼するもの
これらの物質には、適切なラベル表示や指定数量による規制が課されており、取り扱う際には所定の資格や設備を整える必要があります。
参考:e-Gov 法令検索|消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
【関連記事】危険物になるアルコール製剤とは?取り扱い方と保管方法を解説
消防法に定められている危険物
危険物は、その性状によって、下記の6つに分類されています。
- 【第一類】酸化性固体
- 【第二類】可燃性固体
- 【第三類】自然発火性物質及び禁水性物質
- 【第四類】引火性液体
- 【第五類】自己反応性物質
- 【第六類】酸化性液体
詳しく解説します。
【関連記事】消防法とは?基本内容と罰則についてわかりやすく紹介
【第一類】酸化性固体
酸化性固体は、自身は燃焼しませんが、ほかの物質の燃焼を促進する性質をもつ固体です。おもに酸素を供給する作用により、火災時の燃焼を加速させるおそれがあります。代表物質は、下記のとおりです。
- 硝酸カリウム
- 塩素酸ナトリウム
- 過マンガン酸カリウム
可燃物や有機物と接触すると、摩擦や衝撃、加熱によって激しい発火や爆発の危険があります。工場・倉庫では必ず分離保管が求められ、湿気による劣化・反応にも注意が必要です。
【第二類】可燃性固体
可燃性固体は、火炎などによって着火しやすく、燃焼速度が速い性質をもつ物質です。とくに粉末や繊維状のものは着火性が高く、静電気でも発火することがあります。
- 硫黄
- 赤リン
- 固形アルコール
- ラッカーパテ
酸化剤との混在や摩擦、火気接近により、急激な燃焼や爆発が発生するおそれがあります。静電気対策や湿度管理、換気の確保など、複数の安全対策が不可欠です。
【第三類】自然発火性物質及び禁水性物質
第三類の危険物は、空気や水と反応することで発火・爆発するおそれがある物質です。極めて取り扱いが難しく、保管環境に細心の注意が求められます。
- ナトリウム
- 黄リン
- アルキルアルミニウム
自然発火性物質は空気中で発熱・発火し、禁水性物質は水と反応して可燃性ガスを発生させます。水による消火は禁忌であり、粉末消火剤や乾燥砂での対応が求められます。密閉保管と空気遮断が基本です。
【第四類】引火性液体
液体またはその蒸気が、火花や静電気で引火する性質をもつ危険物です。消防法上、もっとも広く管理対象とされるのがこの第4類です。
- 特殊引火物(アセトアルデヒド)
- 第1石油類(ガソリン)
- 第2石油類(灯油)
- 第3石油類(重油)
- アルコール類(メタノール)
蒸気は空気より重く、床面や低い場所に滞留しやすいため、火花が届きやすく爆発のリスクがあります。保管・作業場所では換気、密閉、アース処理、火気厳禁の徹底が必要です。
【第五類】自己反応性物質
外部の酸素を必要とせず、自らの化学反応によって発熱・発火する性質をもつ危険な物質です。わずかな刺激で爆発事故につながる可能性があります。
- ニトログリセリン
- トリニトロトルエン(TNT)
- ヒドロキシルアミン
加熱・衝撃・摩擦といった物理的刺激によって分解が始まり、爆発的な反応を引き起こします。気温や振動など外部環境にも敏感なため、冷暗所での静置保管が求められます。大量保管は避け、厳格な取り扱い管理が必須です。
【第六類】酸化性液体
酸化性液体は、自らは燃えませんが、ほかの物質の燃焼を促進させる性質があります。腐食性や有害性をあわせもつものも多く、取り扱いには保護対策が求められます。
- 過酸化水素
- 硝酸
- 過塩素酸
強い酸化作用により、可燃物との接触で発火や爆発を引き起こす危険があります。また、金属や人体に対しても腐食性・毒性をもつため、耐酸容器の使用や保護具(手袋・マスク・ゴーグルなど)の着用が義務づけられる場合があります。
消防法における危険物施設とは
消防法における「危険物施設」とは、危険物を製造・貯蔵・取り扱うために設けられた場所や設備のことを指します。
具体的には、下記のような施設に分けられています。
- 製造所
- 貯蔵所
- 取扱所
これらの施設を新たに建設する際には、消防署への届出や設置許可が必要です。また、それぞれの施設に応じて構造・設備・設置基準が細かく定められています。
危険物施設には、災害発生時のリスクを最小限に抑えるため、防火壁・避雷設備・安全距離の確保なども求められます。規模や扱う危険物の量によっては、保安監督者や危険物取扱者の配置も義務づけられるため、厳格な管理体制が必要です。
危険物の表示義務とは
危険物を保管・使用・運搬する際には、消防法により「表示義務」が課せられています。危険物の存在を周囲に明示することで、火災や爆発、中毒といった事故の発生を未然に防ぐための重要な措置です。
表示対象や表示内容の例は、下記のとおりです。
| 表示対象 | 表示すべき内容 |
| ・保管場所(倉庫・屋外貯蔵所など) ・容器やタンク、配管などの設備 ・危険物施設内の掲示スペースや管理室 | ・危険物の品名及び類別 ・危険性の内容(引火性・酸化性など) ・指定数量の倍数 ・取り扱い上の注意事項(火気厳禁・禁水など) |
施設の種類や運用形態に応じて、標識や掲示板などの表示方法も義務づけられます。日常の安全管理だけでなく、災害時の初動対応や消防活動の迅速化にもつながる重要な役割を果たします。
表示義務に違反した場合は、消防機関から下記の行政・刑事措置が科される可能性があるため、注意が必要です。
- 是正命令・改善指導:表示内容の修正や掲示方法の見直しなど
- 改善措置を怠った場合:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
参考:e-Gov 法令検索|消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
これらは、消防法第16条の6(技術上の基準違反)及び第45条(罰則規定)に基づいて適用されます。
そのため、危険物表示の適正な設置と維持管理は、法令遵守と事業継続の両面で不可欠です。定期的な点検・更新を通じて、安全管理体制を強化しましょう。
危険物の表示の種類
消防法では、危険物の保管・取り扱い施設に対して表示義務があります。施設の種類や運用状況に応じて、おもに下記4つの表示方法が定められています。
- 標識
- 掲示板
- 旗
- チャート
詳しく見ていきましょう。
標識
「標識」は、製造所や取扱所、移動タンクなどに設置することが義務づけられている表示です。設置基準は、消防法や関連政令で明確に定められており、遠くからでも識別可能なように設計されます。
具体的な例は、下記のとおりです。
- 移動タンク:黒地に黄色文字の「危」マーク(30cm以上)が必要
- 給油取扱所:白地に黒文字で施設名や取扱危険物の種類などを明示
標識は、現場での初期対応や緊急時において、消防隊が迅速に判断・対応するための重要な情報源です。
参考:e-Gov 法令検索|消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
掲示板
「掲示板」は、危険物を取り扱う施設や倉庫に設置され、保管内容や注意事項を詳細に示すものです。掲示板には、下記のような情報が表示されます。
- 危険物の類別・品名
- 指定数量とその倍数
- 取り扱い上の注意事項(火気厳禁、水との接触禁止など)
- 保安監督者の氏名や職名
掲示板は縦60cm×横30cm以上、白地に黒文字が基本です。必要に応じて赤や青で注意事項を色分けします。法令に基づき設置されており、作業者への注意喚起だけでなく、保安教育や安全巡視の指標としても活用されます。
旗
「旗」は、臨時的な作業場所や一時的な危険物の運搬・取り扱い時に使用される表示です。たとえば、仮設の給油所や一時保管場所など、常設の標識設置が困難な場合に用いられます。
目立つ位置に掲げることで、周囲の作業者や第三者に対し、危険物の存在と危険性を視覚的に周知します。旗には、危険物の類別や注意事項(火気厳禁・禁水など)が記され、色とデザインは法令で定められているのが特徴です。
現場の作業者や周囲への視覚的な注意喚起に効果的で、事故防止のためにも欠かせない措置です。
チャート
「チャート」は、消防法に明記された義務表示ではありません。ただし、複数の危険物を保管・取り扱う事業所では、管理状況を視覚的に整理する実務的な表示方法として広く活用されているのが特徴です。
通常は、施設の中央部や管理室などに掲示され、下記のような情報を一覧でまとめます。
- 危険物の類別・品名
- 最大保管数量と指定数量の倍数
- 緊急時の対応手順(初動対応・避難誘導など)
- 消防機関・保安責任者の連絡先
チャートは、災害発生時の判断支援や、巡視・教育時の情報共有にも効果的です。多種の危険物を扱う中・大規模施設では、チャートの活用が安全管理体制の「見える化」に役立ちます。結果として、リスク管理の強化にもつながるでしょう。
危険物の指定数量
「指定数量」とは、消防法により危険物の種類ごとに定められた基準量のことです。指定数量を超える場合、下記のような追加の安全対策・法的義務が発生します。
- 消防署への届出または許可申請
- 危険物倉庫など適法な施設での保管
- 危険物取扱者(乙種・甲種など)の配置
- 指定の消火設備(泡消火設備・屋内消火栓等)の設置
- 危険物表示(標識・ラベルなど)の明示
指定数量は、物質ごとの性質や危険性に応じて細かく定められています。代表的な危険物と指定数量の例は、下記のとおりです。
| 類別 | 品名(代表例) | 性質 | 指定数量 |
| 第一類 | 硝酸カリウム | 第1種酸化性固体 | 50kg |
| 第二類 | 硫黄 | 可燃性固体(第1種) | 100kg |
| 鉄粉 | 可燃性固体(第2種) | 500kg | |
| 第三類 | 黄りん | 第1種自然発火性・禁水性物質 | 20kg |
| カリウム | 第1種自然発火性・禁水性物質 | 10kg | |
| 第四類 | ガソリン(第1石油類) | 引火性液体・非水溶性 | 200L(危険等級Ⅱ) |
| メチルアルコール | アルコール類・水溶性 | 400L(危険等級Ⅱ) | |
| 灯油(第2石油類) | 引火性液体・非水溶性 | 1,000L(危険等級Ⅲ) | |
| 動植物油 | 引火性液体(第4石油類) | 10,000L | |
| 第五類 | 過酸化ベンゾイル | 第1種自己反応性物質 | 10kg |
| 第六類 | 過塩素酸 | 酸化性液体 | 300kg |
複数の危険物を取り扱う場合は、それぞれの「指定数量に対する実量の比率(=指定数量の倍数)」を算出し、合計が「1」を超えるかどうかで規制対象か判断されます。
ガソリンを100L、灯油を600L保管している場合、指定数量の倍数の算出方法は、下記のとおりです。
- ガソリンの倍数:100L÷200L=0.5
- 灯油の倍数:600L÷1,000L=0.6
合計は、0.5+0.6=1.1となり、指定数量の合計が「1」を超えるため、消防法に基づく規制対象となります。保管にあたっては、消防署への届出・許可や、消火設備の設置、危険物取扱者の配置などが必要です。
また、危険物を取り扱う施設では、危険物の種類・数量・倍数などを見やすく掲示することが求められます。これは緊急時の初期対応や消防活動を迅速化するために不可欠です。
危険物のラベル
危険物の保管容器や運搬容器には、消防法及びGHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム)に基づき、ラベル表示が義務づけられています。ラベルには、製品の特性や危険性を正確に伝える情報を記載する必要があります。
代表的な危険物についてのラベル記載内容の例は、下記のとおりです。
| 製品名(品名・化学名) | 危険物の種類・危険性 | 取り扱い・保管方法 |
| メチルアルコール(メタノール) | 第四類 アルコール類危険等級Ⅱ水溶性あり | 火気厳禁密栓直射日光を避け冷暗所に保管換気のよい場所で使用 |
| ガソリン | 第四類 第1石油類危険等級Ⅱ非水溶性 | 火気厳禁静電気対策必須金属容器に密栓保管通気性良好な冷暗所 |
| 灯油(ケロシン) | 第四類 第2石油類危険等級Ⅲ非水溶性 | 火気厳禁密閉容器で冷暗所に保管加温・加圧禁止 |
| 黄りん | 第三類 自然発火性物質空気接触厳禁禁水性 | 空気遮断(油中保存等)火気厳禁通風のよい場所で冷暗所保管 |
| カリウム | 第三類 禁水性物質水と反応し発火・可燃性ガスを生成 | 禁水油中保存乾燥状態で保管耐火構造の密閉容器に格納 |
| 硝酸アンモニウム | 第一類 酸化性固体可燃物接触注意 | 可燃物と隔離湿気を避ける通風のよい冷暗所に保管 |
| 過酸化ベンゾイル | 第五類 自己反応性物質火気厳禁衝撃注意 | 遮光容器冷暗所に保管衝撃・摩擦を避けるほかの薬品と隔離 |
| 塩素酸カリウム | 第一類 酸化性固体可燃物接触注意衝撃注意 | 火気厳禁衝撃を避ける密閉容器に保管可燃物と分離して保管 |
これらの表示は、作業者が物質の危険性を正しく把握し、必要な安全対策を講じるために不可欠です。視認性の高いラベルデザインと正確な情報記載は、安全管理の要といえるでしょう。
消防法に基づいた危険物の取り扱い方法
危険物は火災や爆発などの重大事故を引き起こすおそれがあるため、その保管・運搬には厳格なルールが定められています。消防法では、指定数量以上の危険物を扱う場合、所轄の消防機関への届出や許可が必要です。
また、指定数量未満でも、地方自治体の条例によって一定の安全基準が課されることがあります。ここでは、「保管」と「運搬」に分けて、具体的な取り扱い方法を解説します。
危険物の保管
危険物の保管には、消防法で定められた基準に適合した施設が必要です。指定数量以上の危険物は、製造所や貯蔵所、取扱所として認可された場所に限り保管が可能です。
これらの施設では、下記のような安全基準が義務づけられています。
- 防火構造や耐火性能の確保
- 消火設備(スプリンクラー・消火器など)の設置
- 周囲の建物との距離(離隔距離)の確保
また、消防長または消防署長の承認を受ければ、10日以内の短期間に限り、仮設での保管・取り扱いも認められます。
指定数量未満の危険物であっても、条例による規制があります。容器の材質や保管場所の構造、表示の掲示義務などが細かく定められており、それぞれを確実に守ることが重要です。
危険物の運搬
危険物を運搬する場合には、指定数量未満であっても消防法の規制対象となります。安全に運ぶために、下記のようなルールがあります。
- 容器は漏れ・破損を防ぐ基準適合品を使用すること
- 積載時は転倒防止や固定措置を施すこと
- 危険物取扱者が同乗し、免状を携帯すること
- 車両には消火器や応急用具を備えること
- 車体には「危険物運搬中」の警告表示を行うこと
タンクローリー(移動タンク貯蔵所)による運搬も同様に、標識の掲示と危険物取扱者の同乗が必要です。万が一、運搬中に事故が発生した場合には、ただちに応急措置を行い、消防機関へ通報する義務があります。
危険物の取り扱いに必要な資格
消防法によって、一定数量以上の危険物を取り扱うためには「危険物取扱者」の資格が必要です。資格には、下記の3種類があり、取り扱える危険物の範囲や、無資格者への監督権限は異なります。
- 甲種
- 乙種
- 丙種
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
甲種
甲種危険物取扱者は、すべての危険物を取り扱える最上位の国家資格です。この資格をもつことで、無資格者の作業に対する立会いや、施設の「危険物保安監督者」への選任が可能となります。
そのため、製造所や貯蔵所、大型化学プラントなど、高度な安全管理が求められる施設で重宝されます。受験には「大学等で化学系課程を修了している」「一定の実務経験がある」などの条件があり、難易度も高めです。
取得できれば、危険物に関わるあらゆる現場で活躍できるため、技術職や設備管理職のキャリアアップを目指す方にとって有効な資格です。
乙種
乙種危険物取扱者は、危険物の性質ごとに分かれた6つの「類」から、特定の1類ごとに取得する資格です。たとえば、第4類(引火性液体)を取得すれば、ガソリンや灯油、アルコール類などの取り扱いが可能になります。
取得した類の危険物に限って取り扱いが可能ですが、無資格者の作業に対する立会いも認められています。とくに第4類はガソリンスタンドや塗装業、化学工場などでの需要が高く、実務に直結する資格です。
受験資格に制限がないため、未経験者や学生でもチャレンジできます。必要に応じて複数の類別を取得することで、対応範囲を広げられます。
丙種
丙種危険物取扱者は、第4類危険物のうち「特定の引火性液体」に限定して取り扱える資格です。対象となるのは、ガソリンや灯油、軽油などで、おもに燃料取扱業務で活用されます。
乙種や甲種とは異なり、無資格者の立会いや保安監督者への選任権限はありません。なお、ガソリンスタンドや灯油配送業務など、現場実務では高い需要があります。
大きな特徴は、受験資格が一切なく、年齢や学歴、実務経験を問わず誰でも受験できる点です。そのため、初めて資格取得を目指す方や、現場経験を積みながらステップアップしたい方に適している資格といえます。
まとめ
危険物を取り扱うには、消防法に基づく厳格なルールと安全管理が求められます。一定の量を超える場合は、専門の施設で保管し、所轄の消防署への届出や許可が必要です。
また、数量が少なくても、条例で定められた基準に従わなければいけません。表示や保管、運搬のルールを正しく理解し、日頃から安全管理を徹底しましょう。消防法を遵守することは、事故の未然防止と事業の信頼性向上につながる重要な取り組みです。
「ワールドシェアセリング」では、元消防職員や有資格者が在籍しており、危険物保管庫の設計から申請、設置までを一貫してサポートしています。現場に即した対応力と豊富な実績があり、消防法に準拠した安全な保管環境を構築可能です。
「どの保管庫を選べばよいか分からない」「消防との協議が不安」といった課題にも対応していますので、気軽にご相談ください。